基本的人権の保障についてまとめています。
基本的人権と個人の尊重
人権を保障するということの「個人の尊重」の原理に基づいて、基本的人権が保障されている。
➋法の下の平等…憲法第14条のは、全ての国民の平等を定める。
人権は全ての人に保障される→社会の中で弱い立場にある人々にとっては、特に大切である。
「子ども(児童)の権利条約」は、1989年に国際連合で採択され、日本も1994年に批准。子どもの生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利を定める。
平等権
平等に生きる権利は、全ての人が持つ平等なあつかいを受ける権利を、平等権という。平等権に反する差別をなくさなければならない。
被差別部落出身者に対する、就職や結婚などでの部落差別。江戸時代の「えた身分」「ひにん身分」に由来、同和問題ともいう。部落差別→1965年、同和対策審議会の答申において, 部落差別をなくすことは国の責務であり、国民の課題であると宣言された。
北海道などに古くから暮らすアイヌ民族に対して、伝統的な風習などを禁止→1997年に制定されたアイヌ文化振興法は、アイヌ文化の振興と伝統の尊重を目指す。
在日韓国・朝鮮人の中には、日本の韓国併合による植民地支配の時代に、日本への移住を余儀なくされた人々とその子孫も多い。就職や結婚などでの差別→歴史的事情を配慮して人権を保障することが大切。
いまだに性別役割分担の考えが残る。「男性は仕事、女性は家事と育児」 。採用や昇進などで女性が不利。セクシュアル・ハラスメントも問題→1985年「雇用機会均等法」、 1999年「 男女共同参画社会基本法」制定。男女が対等に参画し活動できる社会をめざし、育児休業の取得促進、保育所の整備などが求められる。
自立と支援のために障害者基本法を制定。
➋ノーマライゼーション…障がいのある人もない人も区別されることなく,社会の中で普通の生活を送ること。
1980年代後半以降、アジアの人々や南アメリカ(ブラジルやペルーなど)、中国やフィリピンなどの日系人が増加→学校や職場での差別をなくす。社会保障などに配慮。たがいに尊敬し助け合う共生社会の実現→言葉や文化・性別・年齢・障がいの有無などに関係なく利用できるユニバーサルデザインの試み。
自由権
自由に生きる権利の自由権とは、私たちが自由に考え行動することを保障する権利→個人として尊重され、人間らしく生きていくためには欠かすことができない。
- 精神の自由…自由に物事を考えたり、思想や信仰を持ったり、団体を作ったり、自分の意見を発表したりすることを保障。
思想信条に関する内心の自由をめぐる争いの例として三菱樹脂事件が挙げられる。この三菱樹脂事件に関して最高裁判所は、憲法の人権規定は私人間に直接適用されず、企業は特定の思想信条を有する労働者を、それを理由に雇用しなくても違法ではないという判断を示した。
➋信教の自由
信教の自由に関しては、国家の非宗教化を確立することで、個人の信教の自由を制度的に保障 する政教分離もしばしば問題となっている。政教分離の原則が争われた裁判の例として、津地鎮祭訴訟が挙 げられる。津地鎮祭訴訟では三重県の津市が行った地鎮祭について、単なる習俗であり政教分離の原則に反しないという合憲判決を下した。
➌表現の自由
表現の自由とは、考えたことなどを外部に表して他人に伝える自由である。表現の自由の獲得は、検閲の廃止を求めることから始まったとされる。検閲とは、政府などの公権力が表現物を事前に審査し、必要があれば差止めを行うことである。
- 身体の自由…正当な理由なくとらえられたり、無実の罪で刑罰を受けたりしないことを保障。
- 経済活動の自由…自分の住む場所や職業を自由に選ぶ権利や財産権(金や土地などの財産を持つ権利)を保障。精神の自由に比べて法律で広く制限される。
社会権
社会権は人間らしい生活を営む権利。日本国憲法は、社会権として、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権を保障。
- 生存権…「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法第25条)。
- 生活保護法…病気や失業で働けない人に生活に必要な費用を支給。
- 社会保障制度…老齢年金や医療保険、介護保険などの整備が必要。
- 教育を受ける権利…全ての子どもが学校で学習することを保障→教育の基本的な方針は教育基本法で定められている。
- 労働基本権…勤労の権利として働くことを保障。使用者に対して弱い立場にある労働者のための権利で、労働組合を作る権利(団結権)・労働組合が労働条件の改善を求めて使用者と交渉する権利(団体交渉権)・要求の実現のためにストライキを行う権利(団体行動権)がある。
人権保障を確かなものに
- 参政権…国民が政治に参加する権利。議員や知事などを選挙する選挙権。選挙に立候補する被選挙権がある。また, 憲法改正の国民投票権。最高裁判所裁判官の国民審査権、国や地方の機関に要望をする 請願権も参政権にふくまれる。
- 裁判を受ける権利…裁判所に裁判を行うように求める権利。
- その他の請求権…国家賠償請求権、刑事補償請求権。公務員による損害の賠償を請求無罪判決を受けた人が補償を請求。
公共の福祉と国民の義務
「公共の福祉」による人権の制限の人権には、他人の人権を侵害してはならないという限界がある→「公共の福祉」として人権を制限。自由や権利の濫用を認めず、国民は常にそれらを公共の福祉のために利用する責任があると定める(憲法第12条)。経済活動の自由には公共の福祉による制限が広く認められてきたが、精神の自由には限定的にしか認められていない。
- 国民の義務…子どもに普通教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税 の義務一教育と勤労の義務は、同時に権利でもある。
日本の人権問題
民主主義社会とは、ひと言で言えば、すべての人の基本的人権を認めようとする社会のこと、つまり、差別のない社会のことと考えてよい。
現在、日本には女性差別、部落差別、外国人差別、障害者差別など、さまざまな差別がある。それらをなくしていくことが求められている。ただし、現実には難しい問題がたくさんある。個人を尊重すると、ほかのみんなが迷惑することがある。みんなを尊重すると、困る人がでてくる場合がある。そうした際にどうするかが問題になる。みんなの人権をすべて尊重することはできない。
- 法の下の平等…憲法第14条のは、全ての国民の平等を定める。
- だれもが持っている人権…人権は全ての人に保障される→社会の中 で弱い立場にある人々にとっては,特に大切である。
- 子どもの人権…「子ども(児童)の権利条約」は、1989年に国際連合で採択され、日本も1994年に批准。子どもの生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利を定める。
死刑制度
今、そうした問題として議論されてい るのが死刑制度問題だ。死刑制度を存続すべきか。みんなの利益を考えると凶悪犯は死刑にするほうがよい。だが、一人の人間を 死刑にするということは、その人間の最も基本的な生きる権利を奪うということ。
賛成派
死刑廃止を求める人は、こう主張する。 「すべての人の権利を保証するというのが、法の根本理念だ。それを法自身が破ってはいけない。それに、死刑があれば、重罪を防げるという意見があるが、死刑 があっても犯罪が減るわけではない。しかも、死刑にすると、後に無罪だとわかっても取り返しがつかない。そうしたことから、法的に考えれば、死刑を存続すべきではない」
反対派
それに対して、死刑存続論者はこう反 論する。「人を殺して、他者の人権を踏みにじったのだから、自分の人権も否定されて当然だ。危険な人物が生きていると、ほかの人々の権利が否定される恐れ がある。国家は国民全体の利益のために は、重罪人を殺す権利がある」
人権にからむ問題は、以上のように、個人を重視するか、それとも集団の利益を重視するか、という問題が関わっていることを考慮したうえで論じる必要がある。
先進国のほとんどが死刑制度を廃止している。日本もその傾向が強かったが、オウム事件など、凶悪事件の続発のために死刑制度自定論が増えている。
差別用語規制
テレビや新聞などの発の場での差別用語は現在規制されているが、言論の自由のために、規制を緩めるべきだという意見がある。それに対して、差別用語を用いることは、差別を認めたことになるので、規制すべきだという意見が強い。
報道において、容疑者の写真を出すか、容疑段階で実名を報道するかが問題になる。しかし、容疑段階では人権を重視するのが原則だ。

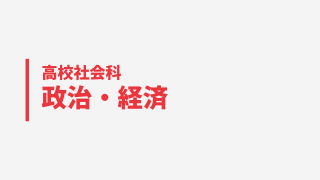
コメント