【共通テスト対策】日本史でよく出る重要用語一覧です。
日本史でよく出る重要用語一覧
- 盟神深湯(めいしんたんとう)…古墳時代の人びとの風習として、鹿の骨を焼いて吉凶を占う太古の法や熱湯に手を入れて真偽を判断する方法
- 古事記…天武天皇のとき古くから伝わる『帝紀』『旧辞」を稗田阿礼に命じてよみならわせたものを、元明天皇が太安麻呂(安万侶)に筆録させたも
- 蘆舎那仏…紫香楽で造立が開始され、平城京に都が戻されたのちに東大寺の大仏として完成した。
- 興福寺…平城京に営まれ、藤原氏の氏寺として藤原氏一族や天皇の信仰も篤く、都が平安京に遷ってからのちも大きな勢力を保った。
- 日本三代実録…中国の史書にならい、編年体で記された六国史の最後
- 坂上田村麻呂・阿倍比羅夫…7世紀に蝦夷を征討した。征夷大将軍となった坂上田村麻呂が胆沢城を築いた。
- 勘解由使…令外官が置かれ、国司の交替を監督した。
- 市司…平城京の左京・右京に設けられた市を監督した。
- 衛士…諸国の軍団から都に上京し、宮門の警備を行った。
- 茶の湯…東山文化期に成立した日本独自の文化であり、千利休が草庵茶室、侘茶を大成した。
- 太閤検地…土地測量の基準が統一され、300歩=反と定められた。1村ごとに耕地の面積などを調査し、従来の高制を石高制に改めた。
- 二条河原落書…文化の担い手の階層が広がったことによって、伝統や故実が軽視されてきた風潮を風刺している。
- 太平記…南北鎌倉幕府の滅亡、朝の動乱を描いた軍記物語である。
- 増鏡…南北朝時代に著された編年体の史書で、承久の乱での朝廷敗北から後醍醐天皇の京都帰還までが描かれている。
- 石山本願寺…摂津に建立され、周心に形式された町は寺内町として発展した。石山本願寺は惣を基盤にして、信者の農民や国人が一揆を結び、大名の支配と闘った。寺院や道場での集まりを中心に、広い範囲に信者の強固な組織を作り上げた。
- 書院造…15世紀後半には、日親の布教活動により、日蓮宗が京都を早い に西日本各地に広まった。この頃、書院造と呼ばれる建築様式) 現れた。
- 北山文化…公家の文化と武家の文化と禅宗をはじめとする大陸の文化が融合した文化
- 加賀の一向一揆…蓮如の布教により広まった一向宗の門徒が中心になって蜂起した。
- 結城合戦…1440年、結城氏が足利持氏の遺児を擁して挙兵したが敗れた。
- 下剋上…実力あるものが、力のばして上の身分の者に打ち勝って、下剋上の風潮が広がりました。
- 戦国大名…守護大名の地位をうばって実権をにぎった者、守護大名が成長した者が各地に登場。応仁の乱以降を、戦国時代といいます。
- 城下町…戦国大名が領国(りょうごく)をつくり、城の周辺に家来を集め、商工業者を呼び寄せ、城下町です。
- 喧嘩両成敗法…紛争当事者が私闘によってその解決をはかることを禁じたものである。
- 桶狭間の戦い…今川義元を破った。
- 長篠の戦い…武田勝頼を破った長篠の戦いは、鉄砲が初めて集団使用されたことで画期的な戦いである。
- 法華一揆…1571年に比叡山を焼き打ちし、法華一揆を弾圧した。
- 検地…戦国大名は農村の支配をいっそう進めるために土地の生産状況を詳しく調べていった。その結果把握された年貢量をもとにして、家臣に支配させる土地の広さや、家臣らに負担させる軍事的装備を決定した。
- 管領…将軍の補佐役。有力な守護が任命されました。
- 侍所…京都を支配し、御家人を統率しました。長官には有力な守護が任命されました。
- 鎌倉府…鎌倉に置かれ、関東の支配にあたります
- 建長寺船…鎌倉時代末期に鎌倉幕府が元に派遣した貿易船である。元寇以後も、日中間の私貿易はさかんに行われていた。
- 段銭…田地1反単位、棟別銭は1軒単位で課された税。幕府はこれらを寺社の造営・修理を名目にしばしば課税し、その一部を収入とした。
- 関銭…交通の要地におかれた関所の通行税である。
- 札差…旗本・御家人から委託を受けて、俸禄米の換金を行った。
- 五カ所商人…京都・堺・長崎・大坂・江戸の商人を指す。
- 千石どおし…近世の農業では穀粒の大きさを選別する農具。
- 千歯扱…米の脱穀に使用する農具として普及した。
- 唐箕…風力を利用してもみ殻や塵芥を除去する農具として普及。
- 農業全書…農学者である宮崎安貞が記した、日本初の体系的な農学書。
- 田中勝介…1610年、徳川家康によってスペイン領の明貴志子(ノヴィスパン)へ通商を求めるために派遣された京都の承認
- 知行合一…理一元論による「知行合一」とは、行動を伴わない知識は本物ではないという実践重視の教えで、朱子の「先知後行」を批判する王陽明の根本思想である。
- 酒井田柿右衛門…上絵付の技法を修得し、赤絵磁器の製造に成功して、有田焼の名を高めた。
- シーボルト…長崎郊外に鳴滝塾をひらいて医学の講義や実際の治療を行い、多くの人材がここで西欧の医学や博物学を学んだ。
- 民本主義…吉野作造が、普通選挙によって国民の意向を政治に反映させることを主張。
- 天皇機関説…美濃部達吉が主張した、主権は国家にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治するという憲法学説。
- 文明開化…明治前期には、新しい風潮の浸透もあり、都市を中心に国民の生活様式は変化を示すようになった。
- 福沢諭吉…慶應義塾を創設して教育に従事したり、『文明論之概略』を著したりするなど、多彩な活動を行った。
- 桂園時代…桂太郎と西園寺公望が交互に首相となった明治時代後期から大正時代初期にかけての約10年間。
- 尊王攘夷運動…天皇を結ぶ尊王論と外国の輸出を排除しようとする攘夷論が結びついて尊王攘夷論運動が起こりました。
- 安政の大獄…大老の井伊直弼が幕府に反対した大名や武士、公家らは処罰。吉田松陰らを処刑。
- 桜田門外の変…安政の大獄に反発した水戸藩の浪士たちが井伊直弼を暗殺。幕府は朝廷との融和を図る公武合体政策を進めました。
- 公武合体…幕府が朝廷との伝統的権威と結びつくことで幕政を維持しようとするつ考え方
- 南京条約…アヘン戦争の結果、イギリスが清に結ばせた不平等条約。
- 太平天国の乱…1851年から1864年、清でおこった洪秀全を中心とする反乱。貧富の差のない平等な社会を目指した。
日本史でよく出る法律・制度一覧
- 改新の詔…改新の詔では京・畿内や地方の行政制度や中央集権的な交通・軍事の制度、新たな租税制度を定めている。 日本海側の蝦夷支配の拠点として、淳足綱・緊舟欄が設けられた。
- 三世一身法…未開地を開墾した場合は三世にわたり、既墾地を開墾しなおした場合には本人一代にわたりその保有を認めた。
- 墾田永年私財法…開墾地の私有を永年にわたって認めた法がだされた。
- 御成敗式目…御成敗式目は、源頼朝以来の先例や武家社会の言に基づき、権勢の有無にかかわらず公平に裁判するために制定された。鎌倉幕府は御成敗式目を基本法題とし、その後は必要に応じて御成敗式目に対する追加法という形で新たな立法を行った。
- 永仁の徳政令…永仁の徳政令が出されたのは、幕府が得宗専制政治を行っていた13世紀で、それにより売却された御家人領を無償で買い戻させた。 徳政令が出された時期には荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し、幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。借上が窮乏化した御家人に対して、所領を担保に金を貸した。
- 分国法…守護代・長尾氏からでて関東管領家をついだ上杉謙信(長尾景虎)は、北条氏や武田氏と戦った。16世紀には結城氏新法度(結城家法度)が制定された。 喧嘩両成敗法は、紛争当事者が私闘によってその解決をはかることを禁じたものである。
- バテレン追放令…「日本は神国である」としてバテレン追放(宣教師)令を出し、宣教師の国外追放を命じ、長崎の教会員定収した。京都・長崎などの商人の、東アジア諸国への渡航を認めた。倭寇などの海賊行為を取り締まった。
- 生類憐みの令…病気の生類を捨てることを禁じ、食料のために魚、鳥、亀、貝を売ることを禁止。
- 大日本帝国憲法…かつて北海道開拓使の長官であった黒田清隆が首相の時に、大日本帝国憲法の発布、および衆議院議員選挙法の公布が行われた。法律の制定には帝国議会の協賛が必要とされた。信教の自由は制限付きで認められていた。陸海空の統帥権は、天皇大権の一つとされた。
- 普通選挙法…1925年に制定された25歳以上の男子に選挙権を与える法律。
- 治安維持法…共産主義の活動などを取り締まる法律。
- 教育基本法…圧制的諸制度の廃止の具体例としては、治安維持法が廃止されたことが挙げられる。自由主義的改革がおこなわれ、教育基本法が定められた。教育理念が明記され、新しい科目である社会科が設けられた。
- 独占禁止法…独占による弊害をなくし、自由競争を促すための法律。公正取引委員会が運用にあたる。
- 労働組合法…労働組合結成の奨励がおこなわれた。敗戦後の日本では労働組合法が制定され、労働者の団結権・団体交渉権が保障された。
- 国連平和維持活動(PKO)協力法…1992年に、国連平和維持活動(PKO)協力法が成立します。PKOへの自衛隊の海外派遣と、その小型武器の所有が認められ、カンボジア、モザンビーク、東ティモールなどに自衛隊を派遣してきました。
- 喧嘩両成敗法…中世および近世の日本の法原則の1つで、紛争当事者が私闘によってその解決をはかることを禁じたものである。
- 人掃令…1591年に、武士の百姓・町人化、農民の移転・転業を禁じる法律。検地、刀狩令、この人掃令により、兵農分離が完成。
- バテレン追放令…「日本は神国である」としてバテレン追放(宣教師)令を出し、宣教師の国外追放を命じ、長崎の教会員定収した。京都・長崎などの商人の、東アジア諸国への渡航を認めた。倭寇などの海賊行為を取り締まった。
- 学制…学制の公布に対しては、各地で学制反対の農民一揆がおこった。学制発布当時の小学校は、授業料を払う必要があった。小学校の就学率は、男子の方が女子より高かった。学制の対象は、士族の子弟のみではなかった。
- 糸割符制度…1604年、ポルトガル商人らの生糸貿易での利益独占を排除するため、幕府が定めた特定商人に一括購入される制度。生糸輸入の特権を与えられた承認の組合は、糸割符仲間という。
- 定免法…幕府は18世紀前半、薬用として朝鮮人参や、凶荒用食物として甘藷(さつまいも)などの栽培を奨励した。幕府は享保の改革で、定免法を採用し、年貢量は増加した。定発法は一定の年貢率で本年貢を課すものであるが、それは永続的なものではなく一定の年限を設けるのが普通であった。町人請負新田などの新田開発が奨励された。
- 公事方御定書…徳川吉宗により町奉行に登用された大岡忠相は、市政改革を行うとともに、裁判の基準となる法典の制定(公事方御定書)などにあたった。
- 足高の制…徳川吉宗は、旗本に対して、役職の標準石高を定め、それ以下の者が就任するとき、在職中の不足分を支給する制度をはじめ、人材の登用と支出の抑制を図った。
- 永仁の徳政令…永仁の徳政令が出されたのは、幕府が得宗専制政治を行っていた13世紀で、それにより売却された御家人領を無償で買い戻させた。 徳政令が出された時期には荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し、幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。
- 荘園整理令…荘園を整理して班田の励行を図る。書類に不備がある荘園や、正式な手続をふまずに設立された荘園を没収して公領とした。
- 警察法…警察法が制定され、自治体警察が置かれた。枢密院・貴族院は廃止された。GHQによって社会主義者などの政治犯は釈放され、特別高等警察も廃止された。
- 学校教育法…戦後の改革では、学校教育法が制定された。第二次世界大戦後、教育の民主化を進めるため、都道府県・市町村に公選の教育委員会が設置された。米軍による占領下では、各地方自治体ごとに教育委員会が設置され、また6・3制により義務教育が9年に延長された。国民学校が小学校へと改められた。

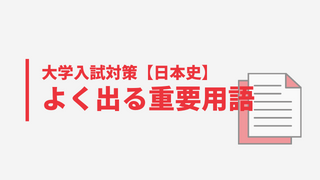
コメント