【高校古文】古文の省略された主語の補い方です。
古文の主語の補い方
古文は、いろいろと省略が多いですが、今回は、省略された主語の補い方です。
【1】同じ主語を補うものと【2】違う主語を補うものがあります。
【1】同じ主語を補う
「て、」や「で、」の前後の主語は基本同じです。例外はもちろんあります。
<例1>
(例文)阿闍梨これを見て、悲しみの涙を流しつつ車よりおりて、あはれみ訪ふ。(発心集)。
(訳)阿闍梨は、この人たちを見て、阿闍梨は、悲しみの声を流しながら車から降りて、阿闍梨は、気の毒がりを見舞う。
この「て」の前後の主語は、全部「阿闍梨」となります。
<例2>
(例文)八日。さはることありて、なほ同じ所なり。(土佐日記)
(訳)八日。さしつかえることがあって、(私は、)依然として同じ所に留まっている。
【2】違う主語を補う
「を、に、が、ど、ば」の前後で主語は変わります。つまり、ある接続助詞の前後で主語が変わるということです。
<例1>
(例文)かの人の入りにし方に入れば、塗籠あり。そこにみて、もののたまへど、をさをさ答へもせず。(宇津保物語)
(訳)(男が)あの女の入っていった方に入ると、塗籠(壁で囲まれた部屋)がある。そこに座って、(男が)何がおっしゃるが、(女は)ほとんど返事もしない。
<例2>
(例文)城崎に来て見れば、やどりは昔ながらにて、もと見し人はあらず。たまたま、「君われを忘れずや」といふを、見れば、むかしの人なり。(藤斐冊子)
(訳)(私が)城崎に来て見ると、宿は昔のままで、前に会った人はいない。たまたま、 誰かが「あなたは私を忘れたのか」というので、私が見てみると、(その話し手は)昔知り合った人である。

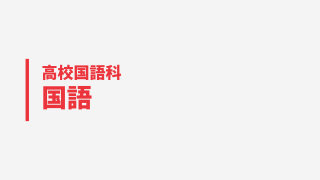
コメント