【2025年度共通テスト】生物基礎の出題傾向と対策ポイントです。
- 知識を問われる問題が多い
- 実験考察問題が増加か
- 計算問題にも注意(典型問題は解けるように)
- 特定の分野に偏ることなく、幅広い内容で出題
共通テスト生物の対策ポイント
何といってもまずは教科書です。教科書は、思っている以上に多くの情報量が載っている。共通テストでは「発展」や「コラム」といった内容は、テスト前には読んでおきたいところです。合わせて、国公立大・2次・私立大の試験対策として、欄外の注釈なども貪欲に学習しておきましょう。
それと並行して図表集も有効も大変有効です。図や写真など目から入ってくる情報は印象に残りやすいです。それらを用いながら、自分流のオリジナルノートを作ってみるのも一つでしょう。
きれいでなくてもいいので、問題集で間違ったところやなかなか理解できない箇所を、自分なりの図などを用いてノートに書き留めていこう。後はそれをいつでもどこでも何度でも見るようにしましょう。
教科書の活用
隅から隅まで読み込んで 丁寧にそして貪欲に吸収することがポイント!
教科書の情報量は思っている以上に多く、また、最終的に入試問題は教科書を参考にして作られている。細かい知識が出題されたと思っても、よく教科書を見てみると載っているものが多い。
太字で書かれた重要用語だけでなく、欄外の小さな文字で書かれた注釈まで、本当に隅から隅まで、丁寧に、貪欲に、すべてを吸収するつもりで何度も読み込んでもらいたい。重要用語はその定義、使われ方にも意識すること。 それが論述対策にもなるのだ。
また、重要な図やグラフは自分のオリジナルノートに描き写してみよう。自分で描くことでインプットされやすくなるのである。何といってもすべての基本は教科書である。
図表集の活用
図や写真は覚えようとしなくても 眺めているだけでも有効です!
図表集には、教科書にも記載がないような発展的な内容も載っている。それらは覚えておかなくても、実験考察問題の際に有効になる。また、きれいな写真などはそれだけで興味をそそり、気楽に眺めるだけでもインプットされやすくなる。
オリジナルノートの作成
自分で書いた字や図が インプットされやすいので、教科書と図表集をもとに自分流のノートを作ろう。メモ程度でよいので、間違ったところ、気になったところなどをどんどん書き込んでいこう。後はそれを常に持ち歩いて、何度も何度も繰り返して見直せば万全である。インプットの極意は繰り返しである。
アウトプットを意識
知識のインプットと同時に、アウトプットの練習も行う必要がある。具体的にはまず1冊標準的な問題集を用意し、小さな単元を学習したらすぐに問題を解いてみよう。
問題を解くことでさらに知識も定着し、どのように問われるかがわかるようになります。そこで間違えた問いがあれば、すぐさまノートにメモすることを忘れないこと。さらによく犯してしまうようなミス、例えば単位を間違えたということがあれば、それもノートに「単位に気を付けろ!」というようにメモしていくとよいでしょう。
また、テレビでもよく生物関係の番組があるので、息抜きもかねて、そのような番組を見ることも有効である。興味がわくとインプットされやすくなるものです。
グラフを書く
教科書に登場する重要なグラフは、それほどたくさんあるわけではありません。
それらのグラフをただ「見たことがある」だけで終わらせず、
- 縦軸は何か。
- 単位は何か。
- どのような測定をしたからこのようなグラフになったのか。
といったことにも注意を払いながら、やはり自分でそのグラフを描いていきましょう。
すると縦軸、横軸、単位などがちゃんとインプットできますし、なぜここで傾きが変わるのだろう? という疑問もわいてきます。それらを一つひとつクリアにしていくと、初見の問題も多い印象の共通テスト本番で、新しい見たことがないグラフが登場してもちゃんとその場で解読できるようになります。

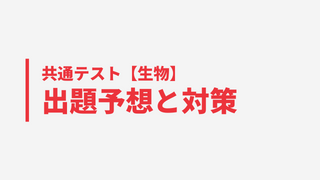
コメント