【高校日本史】飛鳥時代の問題です。
【対策問題】飛鳥時代の問題
【問1】推古天皇の時代におこなわれた遣隋使の派遣は、5世紀の倭王武による宋への使節派遣以来、約120年ぶりのことだが、隋への使節派遣の背景について、「倭の五王」の時代との違いを含め、以下の国名(王朝名)を用いて80字以内で説明しなさい。
王朝名:(隋)(高句麗)(百済)(新羅)
【問2】次の問いに答えなさい。
- 6世紀中ごろに、朝鮮半島への政策の失敗が原因で勢 力を失ったとされる豪族は何氏か。
- 6世紀中ごろ、ヤマト政権内で仏教受容などをめぐって対立した大臣と犬達の豪族はそれぞれ何氏か。
- 皇位継承問題で対立した大連の物部守屋を攻め滅ぼし、592年には自分たちが擁立した天皇を殺害した人物は誰か。
- 蘇我馬子に殺害された天皇は誰か。
- 崇峻天皇が暗殺されたあと、群臣に擁立されて即位した最初の女性天皇は誰か。
- 蘇我馬子とともに国政にあたった推古天皇の甥にあたる人物は誰か。
- 603年に定められた氏族ではなく、個人の才能・功績により冠位を与えるとした人材登用の制度を何というか。
- 604年に定められた天皇への服従、衆議尊重、仏法僧崇敬など、官人への道徳的訓戒を内容とした法令を何というか。
- 589年に、中国の南北朝を統一した王朝を何というか。
- 推古天皇の時代に隋の王朝に派遣された使節を何というか。
- 607年、遣隋使の使節として派遣されたのは誰か。
- 608年に派遣された県逗子の使節に同行して隋に渡った習学生の名をあげよ。
- 高向野玄の人物とともに隋に渡った学問僧を2人をあげよ。
- 遣隋使の記事などを載せている中国の歴史書は何か。
- 618年、隋にかわって中国を統一し、都を長安に置いて繁栄した王朝を何というか。
- 第1回遣唐使として派遣されたのは誰か。
- 17世紀前半の推古天皇の時代を中心に展開した文化を何というか。
- 氏族が一族のために建立し、その帰依を受けた寺院を何というか。
- 蘇我氏の発願によって建立された本格的な伽藍をもつ寺院を何というか。
- 厩戸王(聖徳太子)の発願といわれる現在の大阪市に所在する寺院を何というか。
- 厩戸王の発願により大和斑鳩の地に建立された寺院を何というか。
【問3】大宝律令でめざした徴税などの律令体制は、10世紀には現実的な修正を迫られていた。そのうち10世紀における人民や土地の支配方法の変化や、地方支配は誰 がになうようになったのかについて,以下の語句を必ず用いて80字以内で説明しなさい。
【問4】次の問いに答えなさい。
- 701年、律6巻・令11巻が完成し、律令政治の仕組みもほぼ整った。この律令を何というか。
- 大宝律令の律令の編纂に際し、中心となった人物を2人あげよ。
- 律令により運営される国家を何というか。
- 718年に成立し、757年に施行された律令を何というか。
- 養老律令の律令を作成した人物と施行した人物は誰か。
- 律令制度の中央官制の組織を官庁の数でまとめて何というか。
- 二官とは神武祭祀を司る言と、一般行政の最高機関である言を指すが、それぞれの名称をあげよ。
- 太政官のもとで、政務を分掌した中央行政官庁を総称して何というか。
- 官史の不正を監視する機関を何というか。
- 京内・宮中のこをおもな職務とした役所を何というか。
- 太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣と大納言・中納言・参議・三位以上の者をあわせて何というか。
- 一般に五位以上の位階をもつ者を何というか。
- 朝廷が置かれた京周辺の国々を何というか。
- 畿内以外の行政区を総称して何というか。
- 畿内・七道の行政区は、さらに細分化された。広い順に3つの行政区をあげよ。
- 国内の統治行政のために中央から派遣された地方官を何というか。
- 律令制下の諸国の役所またはその所在地を何というか。
【解答】飛鳥時代の問題
【問1】隋帝国の統一により、高句麗・百済、続いて新羅が使節を派遣して朝貢し、冊封を受けた。これにより情を中心とする国際秩序が形成されたが、日本は冊封を受けなかった。
【問2】
- 大伴氏
- 大臣:蘇我氏、大連:物部氏
- 蘇我馬子
- 崇峻天皇
- 推古天皇
- 聖徳太子
- 冠位十二階
- 憲法十七条
- 隋
- 遣隋使
- 小野妹子
- 高向野玄
- 南淵請安、旻
- 隋書倭国伝
- 唐
- 犬神御田鍬
- 飛鳥文化
- 氏寺
- 飛鳥寺
- 四天王寺
- 法隆寺
【問2】解説
1.『日本書紀』によると、大伴金村は、512年に加耶西部の地域に百済の支配権が確立したことが失政とされ、失脚したとされている。
1.『日本書紀』によると、大伴金村は、512年に加耶西部の地域に百済の支配権が確立したことが失政とされ、失脚したとされている。
2.欽明天皇の時代に仏教が公式に伝えられた際、宗仏派の蘇我稲目と排仏派の物部尾輿とが激しく対立したという。蘇我氏は、稲目・扇子・蝦夷・入鹿の4人が大臣の地位に就任し、権勢をほこった。
7.徳・仁・礼・信・義・智の6徳目を、大小に分けて12階とし、色別の冠を与えた。
11.このときの国書は倭の五王時代のころとは異なり、中国皇帝に臣属しない形式をとっていたため、隋の皇帝場帝が不快感を表したことが、『隋書』倭国伝に記されている。
【問3】戸籍作成と班田収授が滞り、公民を把握できなくなった。郡司の地方行政機能が低下し、徴税請負人化した受領の率いる在庁官人が国衙をにない、公地は負名体制に再編された。
【問4】
- 大宝律令
- 刑部親王、藤原不比等
- 律令国家
- 養老律令
- 作成:藤原不比等、施行:藤原仲麻呂
- 二官八省一台五衛府
- 神祇官、太政官
- 八省
- 弾正台
- 五衛府
- 公卿
- 貴族
- 畿内
- 七道
- 国・郡・里
- 国司
- 国府
【問4】解説
1.律は刑法であり、令は行政組織や官吏の勤務規定、人民の租税や労役の規定などである。
2.大宝律令完成のときの天皇は文武天皇である。
3.日本の場合は、天皇中心の中央集権的官僚制の国家体制であった。
5.養老令は官撰注釈書「令義解』と私撰注釈書『令集解』に大部分が、養老律は一部が伝存する。内容的には大宝律令と大差はない。
7.太政官では、最高官職ではあるが財閥の官である太政大臣、政務を総括した左大臣、右大臣、外記などから構成されていて、公卿会議で審議し、天皇の裁可を得て、の実務を八省に分担させた。
10.国衛門府・左衛士府・右衛士府・左兵衛府・右兵衛府を五衛府という。
1.律は刑法であり、令は行政組織や官吏の勤務規定、人民の租税や労役の規定などである。
2.大宝律令完成のときの天皇は文武天皇である。
3.日本の場合は、天皇中心の中央集権的官僚制の国家体制であった。
5.養老令は官撰注釈書「令義解』と私撰注釈書『令集解』に大部分が、養老律は一部が伝存する。内容的には大宝律令と大差はない。
7.太政官では、最高官職ではあるが財閥の官である太政大臣、政務を総括した左大臣、右大臣、外記などから構成されていて、公卿会議で審議し、天皇の裁可を得て、の実務を八省に分担させた。
10.国衛門府・左衛士府・右衛士府・左兵衛府・右兵衛府を五衛府という。
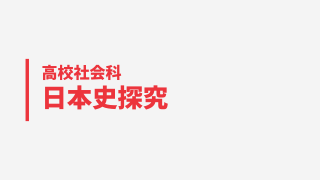
コメント