【2025年度共通テスト】倫理の出題傾向と対策ポイントです。
共通テスト倫理の出題傾向
- 青年期・現代社会分野/源流思想分野/日本思想分野/西洋近現代思想分野の学習が必要
- 全単元、満遍なく出題される傾向
- 思想家についての出題も目立つ
- 現代思想分野はやや難題が多い傾向
共通テスト倫理の対策ポイント
倫理の勉強において、インプット学習に欠かせません。基礎段階において、共通テストの大きな得点ウエイト占める知識問題への対応力をつけることは欠かせません。
そのためには、まず教科書を最低2回は通読し、思想の相違点がわかる学力をつけよう。
1度目は、できるだけ短期間で本文を読み、倫理の学習範囲の全体像をつかむことを目的にする。少々わからないことがあっても、とにかく先に進むことが大切だ。
2度目は、注釈を含め、思想史の部分は精読をします。この段階の目的は曖昧かつ不確かな言葉をなくすことが目的。国語辞書を大いに活用してほしい。2回の通読が終わった時点で、一問一答集を使って学習した知識の定着度を確認し、間違ったものについて、教科書の関連箇所を熟読しよう。
教科書の使い方
学習の中心は教科書の読解。言葉の裏とフレーズのつながりを考えながら読む。
どの教科書も
①青年期に関する議論や心理学説
②古今東西の倫理思想史
③現代社会論に分かれている。
1度目は全分野を通読しよう。①と③の部分の理解は難しくないと思います。
理解の差が出るのが、「古今東西の倫理思想史」。
この分野の学習は、たとえば「アリストテレス:現実主義的な思想を主張」と暗記するのではなく、「アリストテレスは、プラトンのいうイデアの根拠を疑ったから、理想主義の思想ではなく、現実主義的な思想を主張」と覚えよう。
つまり、「~を主張」 する背景(批判の対象)を意識するとともに、「~だから」というフレーズのつながりを頭の中で構築しながら教科書を読解していくことが重要です。
国語辞書の活用
国語辞書を頻繁に活用して語彙力を高めましょう。
知らない言葉を飛ばしたり誤魔化したりする人は学力が伸びない。特に2回目の通読のときには、どんなに時間がかかっても、知らない言葉は国語辞書で調べよう。すぐに効果は現れないかもしれないが、 こうした地道な取り組みが後の大きな推進力となる。
一問一答集の活用
理解が大切とはいえ最低限の暗記も必要。一問一答集で知識を確認しましょう。
倫理は、教科書の記述に基づき思想を理解していくことが最重要である。しかし、最低限の用語を覚えていなければ理解も深まらない。教科書の大学レベルの用語が暗記できているかを、教科書を2度通読した後、一問一答集を使って確認するとよいです。
思考力を養う
確かに倫理で使われている用語は易しくはないし、日常語と意味がずれているときもあります。
しかし、その大半はその言葉でしか新しい思想を表現できなかったものなので覚えるしかないのです。その点、教科書は安易な解釈で誤解を招かないように、可能な限り易しい言葉で書かれているので比較的わかりやすいと思います。
ちなみに、倫理ができるようになると、哲学や思想を扱った文章が読めるようになり、現代文や英語の得点も伸びることがあるので、コンパクトによくまとまった説明がされている国語辞書で、調べることを厭わずに取り組んでほしいと思います。
倫理の対策まとめ
教科書を柱にした学習を。
その基礎学力を問題演習で得点力に結びつけられるようにしていきましょう。現代社会や政経とは異なり、倫理では「臓器移植法が1997年に施行された」などの知識は必要ありません。細かい年号までは問われることもありません。
むしろ、臓器移植が可能になって、「人の死はいつからか」「取り出した臓器の所有権は誰にあるのか」といった法律だけでは解決できない倫理的問題が生じていることを知っておくべきです。
こうした倫理的問題が、数年で大きく変わることはないから、教科書の記述を理解していれば、倫理で出題される現代社会論にも十分に対応できます。あとは、その知識を問題演習で得点力に換えていくだけです。

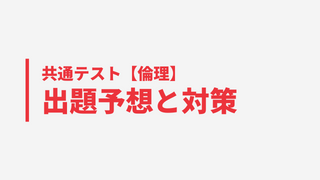
コメント