【日本史探究対策問題】大正時代の問題です。
【対策問題】大正時代の問題
次の( )に適語を入れなさい。ただし、同じ語句は入りません。
(1)東大教授の憲法学者( )は,「主権は国家にあり、天皇は国家の最高機関である」とした( )と政党内閣論を説き、吉野作造の民本主義と大正デモクラシーを支えた。
(2)第3次桂太郎内閣が組閣されると、立憲政友会の( )や立憲国民党の犬養毅を中心として、「閥族打破・( )」を掲げる第一次護憲運動が展開された。
(3)非難をあびた桂首相は( )を結成して対抗しようとしたが、民衆が議会を包囲する中、1913年2月にわずか53日で退陣した。これを( )という。
(4)第2次大隈重信内閣は、( ) を理由に第一次世界大戦への参戦を決定し、ドイツに 宣戦布告後、山東半島膠州湾のドイツの軍事根拠地 ( )を占領した。
(5)ヨーロッパ諸国が中国問題に介入する余力がないのに乗じて、日本は1915年、中国の ( )政府に( )をつきつけ、その大部分を受諾させた。
(6)1919年、朝鮮では( )と呼ばれる大衆運動がおき、中国でもヴェルサイユ条約の内容へ抗議する ( ) が全国に拡大した。
(7)1921年から22年にかけて、アメリカ大統領ハーディングの提唱で海軍の軍備縮小と太平洋及び極東問題を審議するための国際会議である ( ) が開催され、日本からは加 藤友三郎らが全権として出席した。
【問2】日本政府が中国政府に対して1915年に二十一ヵ条の要求を出した当時の国際情勢を60字以内で説明しなさい。
【問3】1895 (明治28)年に成立した第1次大隈重信内閣と1900 (明治33)年に成立した第4次伊藤博文内閣に比べ、1918(大正7)年に成立した原内閣が本格的政党内閣といわれる理由を80字以内で説明しなさい。
【問4】次のア・イ・ウはすべて1897(明治30)年に起きたものだが、これらがこの時期に起きた背景を120字以内で説明しなさい。
ア 貨幣法を改正して金本位制度を導入した
イ 綿糸の輸出量が輸入量を上まわった
ウ 官営八幡製鉄所の建設をはじめた
【解答】大正時代の問題の解答・解説
【問1】
(1)美濃部達吉 、天皇機関説
(2)尾崎行雄、憲政擁護
(3)立憲同志会 、大正政变
(4)日英同盟、青島
(5)袁世凱、二十一 条の要求
(6)三·一独立運動、五·四運動
(7)ワシントン会議
【問2】
欧米諸国は第一次世界大戦のため中国問題に介入できず、辛亥革命後の混乱が続くなかで、日本は中国のドイツ権益を接収していた。
❷第一次世界大戦が開始されると第2次大隈重信内閣は日英同盟協約を根拠にドイツに対し宣戦布告し、山東半島のドイツ権益を接収した。
❸欧米が中国問題に介入する余力のない情勢をみて日本は中国の袁世凱政府に二十一ヵ条の要求をつきつけた。
【問3】
大隈内閣・伊藤内閣はともに藩閥出身者によって組閣された藩閥政治であったが、原内閣は華族でも藩閥出身者でもない平民籍の衆議院議員を首相とする政党内閣であったから。
【問4】
日清戦争後、政府は清国から得た影響をもとに本位制を導入し、賃整価値の安定と貿易の振興を行った。機械制生産を行う大規模工場が設立されて、綿糸の輸出が急増し、官営事工場の拡充と重工業の基難となる影場の国産化による軍備拡張も急がれた。
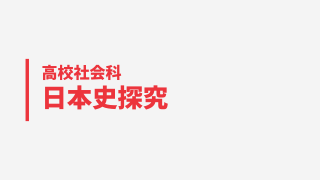
コメント