【高校生用】故事成語一覧(大学入試対応)これだけは覚える!についてまとめています。
故事成語
故事成語は、昔あったことや話が元になってできた言葉のことです。そのあたりについて、まとめています。それでは、大学受験・現代文「故事成語」これだけは覚える!です。
石に漱(くちすす)ぎ流れに枕(まくら)す
<意味>
負け惜しみの強いこと。
<故事>
「石に枕し流れに漱ぐ」を言い間違えたのを指摘され、石に漱ぐのは歯を磨くためで、流れに枕するのは嫌なことを聞いた耳を洗い流すのだと、取りつくろったことによる。 夏目漱石の「漱石」はこの故事によるもの。
「石に枕し流れに漱ぐ」を言い間違えたのを指摘され、石に漱ぐのは歯を磨くためで、流れに枕するのは嫌なことを聞いた耳を洗い流すのだと、取りつくろったことによる。 夏目漱石の「漱石」はこの故事によるもの。
一炊の夢(邯鄲(かんたん)の夢)
<意味>
栄枯盛衰ははかないものだということ。
<故事>
若者が邯鄲(かんたん)という都の宿で不思議な枕を借りて寝ると、良い妻や子を得て出世し栄華を極めて長生きをするという、あこがれの一生の夢を見た。目覚めると、宿の主人があわを炊く間のごく短い時間にすぎなかった。
若者が邯鄲(かんたん)という都の宿で不思議な枕を借りて寝ると、良い妻や子を得て出世し栄華を極めて長生きをするという、あこがれの一生の夢を見た。目覚めると、宿の主人があわを炊く間のごく短い時間にすぎなかった。
臥薪嘗胆
<意味>
敵を討つことを常に考え、また、目的のため、長い間苦労を重ねること。
<故事>
春秋時代の呉の夫差(ふさ)は、父のあだを討とうと、薪(たきぎ)の中に寝て復讐心を持ち、三年後に越王勾践(とんおうこうせん)を会稽山(かいけいざん)で打ち破る。会稽の恥を受けた越王の勾践は、復讐心を忘れないようにと、苦い胆(きも)を嘗(な)めては敗戦したことを思い出し、十数年後に呉王夫差を討ち滅ぼした。
春秋時代の呉の夫差(ふさ)は、父のあだを討とうと、薪(たきぎ)の中に寝て復讐心を持ち、三年後に越王勾践(とんおうこうせん)を会稽山(かいけいざん)で打ち破る。会稽の恥を受けた越王の勾践は、復讐心を忘れないようにと、苦い胆(きも)を嘗(な)めては敗戦したことを思い出し、十数年後に呉王夫差を討ち滅ぼした。
鼎(かなえ)の軽重を問う
<意味>
「鼎(かなえ)」は権力の象徴とされた。権力を持つ者の実力を疑うこと。「鼎の軽重を問われる」とは、実力を再評価される、実力を低く見られる意味にも使う。
<故事>
楚の荘王(そうおう)には天下を取ろうとする野心があり、周王室の県の重さを尋ねたという。
楚の荘王(そうおう)には天下を取ろうとする野心があり、周王室の県の重さを尋ねたという。
画竜点晴(がりょうてんせい)
<意味>
物事を完成させる、最後の仕上げのこと。
<故事>
絵師が竜を描いたが、ひとみを描くと飛び去ってしまうといって描かなかった。人々がそれをでたらめだと言ったためにひとみを描くと、雷鳴電光と共に竜が天に昇った。
絵師が竜を描いたが、ひとみを描くと飛び去ってしまうといって描かなかった。人々がそれをでたらめだと言ったためにひとみを描くと、雷鳴電光と共に竜が天に昇った。
完壁
<意味>
欠点が全くなく、完全なこと。本来は他人からの預かり物を傷つけずに返すこと。
<故事>
「壁」は宝玉を指す。戦国時代に趙の宝玉「和氏の壁(かしのかべ)」を、秦の王が十五の都城と引き換えに欲しいというので、藺相如(りんしょうじょ)が 使者となったが、秦の王は璧を手に入れても都城を渡す気がなかったため、藺相如は王を飲いて璧を取り戻し、無事に趙に持ち帰った。
「壁」は宝玉を指す。戦国時代に趙の宝玉「和氏の壁(かしのかべ)」を、秦の王が十五の都城と引き換えに欲しいというので、藺相如(りんしょうじょ)が 使者となったが、秦の王は璧を手に入れても都城を渡す気がなかったため、藺相如は王を飲いて璧を取り戻し、無事に趙に持ち帰った。
杞憂(きゆう)
<意味>
よけいな心配をすること。
<故事>
杞の国の人が、天地が崩れて落ちるのではないかと心配したことから。
杞の国の人が、天地が崩れて落ちるのではないかと心配したことから。
呉越同舟
<意味>
仲の悪い者どうしや敵味方が同じ場所に居合わせること。
<故事>
春秋時代、仲の悪かった呉の国の人と 越の国の人が同じ舟に乗り合わせたが、あらしに遭って協力して助け合ったことから。
春秋時代、仲の悪かった呉の国の人と 越の国の人が同じ舟に乗り合わせたが、あらしに遭って協力して助け合ったことから。
四面楚歌
<意味>
周りが全部敵で、孤立すること。
<故事>
春秋時代、楚の項羽が漢の高祖の軍に包囲された。夜、漢軍から楚の歌が聞こえ、項羽は楚の人が皆降伏したと思い込んだが、高祖が漢の兵士たちに歌わせたものだった。
春秋時代、楚の項羽が漢の高祖の軍に包囲された。夜、漢軍から楚の歌が聞こえ、項羽は楚の人が皆降伏したと思い込んだが、高祖が漢の兵士たちに歌わせたものだった。
推敲
<意味>
詩や文章を作るとき、何度も字句を練ること。
<故事>
唐の詩人の「かとう」が、僧は推す月下の門」の句の「推す」を「敲く」にしようか悩み、 たまたま会った有名な詩人の韓急に聞いて、「敲く」に決めたことから。
唐の詩人の「かとう」が、僧は推す月下の門」の句の「推す」を「敲く」にしようか悩み、 たまたま会った有名な詩人の韓急に聞いて、「敲く」に決めたことから。
蛇足
<意味>
あっても意味のない、余計なもの。
<故事>
昔、中国でいちばん早く蛇の絵を描き上げた者が酒を飲めることにしたところ、最初に描いた者が時間が余って蛇に足を描いてしまい、酒が飲めなかったことから。
昔、中国でいちばん早く蛇の絵を描き上げた者が酒を飲めることにしたところ、最初に描いた者が時間が余って蛇に足を描いてしまい、酒が飲めなかったことから。
朝三暮四
<意味>
同じものなのに目先を変えただけでその違い に気づかないこと。
<故事>
飼っている猿に「トチの実を朝に三つ、 夕方に四つやろう」と言ったら猿が怒ったので、「朝に四つ、夕方に三つにしよう」と言うと喜んだことから。
飼っている猿に「トチの実を朝に三つ、 夕方に四つやろう」と言ったら猿が怒ったので、「朝に四つ、夕方に三つにしよう」と言うと喜んだことから。
背水の陣
<意味>
決死の覚悟で事にあたること。
<故事>
戦のときは、ふつう山を背に、川を前に陣を敷くが、漢の武将の韓信は川を背に陣を敷き、これ以上逃げ場がないという覚悟で戦いに臨み、敵を破った。
戦のときは、ふつう山を背に、川を前に陣を敷くが、漢の武将の韓信は川を背に陣を敷き、これ以上逃げ場がないという覚悟で戦いに臨み、敵を破った。
矛盾
<意味>
物事のつじつまが合わないこと。
<故事>
楚の国に矛と盾を売る人がいて、「自分の矛はどんな盾も破ることができる」「自分の盾はどんな矛も防ぐことができる」と言っていた。しかし、客に「お前の矛てお前の盾を突いたらどうなるのか」と聞かれると、答えることができなかった。
楚の国に矛と盾を売る人がいて、「自分の矛はどんな盾も破ることができる」「自分の盾はどんな矛も防ぐことができる」と言っていた。しかし、客に「お前の矛てお前の盾を突いたらどうなるのか」と聞かれると、答えることができなかった。
その他のよく出る故事成語一覧
| 故事成語 | 意味 |
|---|---|
| 青は藍より出でて藍より青し(出藍の誉れ) | 弟子が師匠より優れていること。 |
| 悪事千里を走る、 | 悪いうわさはすぐ広まること。 |
| 羹(あつもの)に懲りて膾(なまず)を吹く | 一度の失敗に懲りて、用心しすぎること。 |
| 衣食足りて礼節を知る | 生活が豊かになって、初めて恥や外聞などに目を向けるようになるということ。 |
| 温故知新 | 古いことを調べることで、新しい考えや知識 などを得ること。また、古典や伝統的なものから、新たな価値や意義などを発見すること。 |
| 漁夫の利 | 両者が争う間に、第三者が利益を得ること。故事シギとハマグリが争うところへ漁夫が来て、両方とも難なく捕まえたことから。 |
| 蛍雪の功 | 苦労して学問に励んで成功すること。 |
| 朝令暮改 | 命令がすぐに変わって定まらないこと。 |
| 虎の威を借る狐(きつね) | 権力者の力を盾にいばること。 |
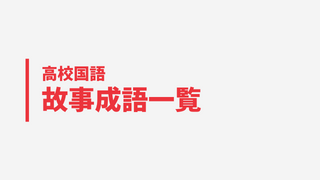
コメント