【高校古文】古文の省略(主語や体言など)まとめ
主語や体言などの省略
「が」の省略
現代語で「~が点をした。」などの「が」にあたる部分が省略される。
(例)今は昔、震旦に漢の高祖と云ふ人有りけり。(今昔物語集)
(訳)今となっては昔のことだが、震の国(中国)に漢の高祖という人がいた。
「の」の省略
現代語で「~の(もの)」にあたる部分が省略される。
(例)風のはげしく吹きけるを見て、(宇治拾遺物語)
(訳)風が激しく吹いたのを見て、
体言の省略
体言(名詞・代名詞のこと)が省略される。
(例)男も女も、若く清げなるが、いと黒き衣着たる、以下省略〉(枕草子)
(訳)男も女も、若々しく美しい人が、たいそう黒い衣を着ている
主語の省略
主語が省略される。
(例1)今は昔、竹取の翁といふものありけり。
(訳1)今となっては昔のことだが、竹取の翁という者がいたそうだ。
(例1)野山にまじりて竹を取りつつ、よろづの事に使ひけり。(竹取物語)
(例2)(竹取の翁は)野山に入って竹を取っては、(竹取の翁はその竹を)色々なことに使っていた。
→主語は省略されてるいこが多いので、補いながら訳をしていきます。
述語の省略
(例)夏は夜。月のころはさらなり、やみもなお、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし。
(訳)夏は夜は趣深い。月のころはいうまでもなく、やみ夜もやはり、蛍がたくさん乱れ飛んでいるのが趣深い。また、たった1匹2匹ぐらい、かすかに光って飛んでいくもの趣深い。
→趣深いをなんども繰り返すため省略。
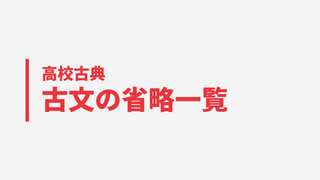
コメント