【大学入試総合型選抜】プレゼンテーションの資料の作り方です。ビジネスやコンテストのプレゼンテーションでは、最終的なゴ-ルは、「共感を得たり、出資を受けたり、ファンを増やたりしていくこと」となる場合が多いです。
一方で、総合型選抜におけるプレゼンテーションでは、最終的なゴールは、「合格すること」です。その合格するために、大事になってくることは、「アドミッションポリシーとの親和性を前提とした論理性」です。これは、志望理由書、論文、面接でも一貫して、問われることとです。
三段論法は論理的思考の基礎というべき技法です。AならばB、BならばC。したがってAならばCという具合のロジックになります。論理性とは、コミュニケーション能力を指すのではないということは、念を押しておきたいです。論理性とは、考えや議論などを進めていく筋道。思考や論証の組み立てであり、思考の妥当性が保証される法則や形式。
プレゼンテーション資料作成のコツ
資料を上手に使っての発表能力自体、大きなセールスポイントになります。うまくいけば、これを堂々と長所と言い放ってもよいでしょう。それに加えて、アイデア力、図解力、演出力などもアピールできる。
最初にタイトルをはっきり示そう。どんな話が始まるのかを最初に伝えることで、その後の話が聞きやすくなる。妙に凝って、わかりにくいタイトルにしないように気をつけよう。
kissの法則
Keep it short and simple(短くシンプルに)
- 資料は、箇条書き(体言止め)・でかく(情報は凝縮する)
- 必要のないものはどんどん削除する。
- 数字は大きく、単位は小さく。
- 囲んで強調しなくていい
- スライドの場合は、最後に「まとめ」があると新設
流れを示す
次に、目次またはチャートでプレゼン全体の流れを示そう。プレゼンの全体像を把握してもらうことで、やはりその後の話が聞きやすくなる。言葉はなるべく少なめにしよう。詳しい説明は口頭で行う。
プレゼン資料は、キーワード、箇条書き、表、図など、なるべく一目で 読み取れるもので構成しよう。見せ方に凝りすぎないようにしよう。特にパワーポイントでプレゼンする場合に、画面切り替え効果やアニメーション効果に凝る人がいる。使用するなとは言わないが、そういった点に凝りすぎて、 肝心の内容がおろそかになっては元も子もなありません。
資料と説明がちぐはぐにならないようにしよう。資料は口頭説明を補足するためにあることを最初に自覚しておこう。資料のどこに注目するとよいのかを明確に伝えよう。たとえば、グラフや表を紹介して、その図の注目点に話がおよんだときは、そこを指し示すなどして、面接官の目がそこに集まるように誘導しよう。
リハーサル
資料を使う場合には、なるべく本番と同じ条件でリハーサルを行い、時間を計りながら、内容、伝え方を調整しよう。パワーポイントを使う場合には、スライドを切り替えるときに、不自然な間を作らないように注意しよう。スライド間をつなぐ言葉(接続詞など)を考えておくとよい。
資料を使う場合の注意
資料ばかり見ていると、照れていると思われる。面接官を見て話すのが基本であることをおさえておこう。ホワイトボードに書こうと思ったらマジックのインキが出ない、持ってきた模造紙が破れていた、パソコンがフリーズを起こしてしまったなど、資料を使うと不運にもアクシデントに見舞われる可能性がある。
そういったときでも集中を切らさないようにしてほしい。想定できるアクシデントが起こったときに、どんな対処法があるかをあらかじめ考えておくとよい。パソコンを使う際には、フリーズした場合に備えて、スライドをプリントアウトした紙を用意していくと安心です。
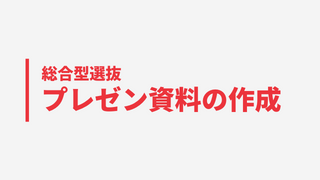
コメント