【高校政経】経済思想のまとめです。
ケインズの経済思想
ケインズは、不況や失業の原因は有効需要の不足にあり、こうした問題を解決するためには政府による積極的な財政・金融政策が必要であると考えた。
そこで、不況時には、公共投資などにより有効需要を増やして、完全雇用を実現すべきと主張した。ニューディール政策では、金利自由化ではなく、この有効需要政策によって景気回復が図られた。
雇用・利子および貨幣の一般理論
ケインズの経済思想で世界恐慌後の1936年、イギリスの経済学者ケインズは著書「雇用・利子および貨幣の一般理論」の中で、有効需要の原理を説き、伝統的な自由放任政策を捨て、政府による積極的な国民経済への介入を主張した。
有効需要とは
実際の貨幣の支出をともなう需要。一国の経済規模(国民所得)は、貨幣の支出を伴う消費需要と投資需要の総和、すなわち有効需要の大きさで決まるとした。消費+投資+政府支出+純輸出(輸出-輸入)の合計。
- 政府による有効需要の創出…失業者が増加し、総需要が低下した場合、有効需要の創出と完全雇用(働く意思と能力をもつ労働者すべてが雇用されている状態)の達成のために、政府支出で公共事業を行って景気を回復させる。
- 混合経済…公的経済部門と民間経済部門の併用。修正資本主義の特徴。
有効需要政策
実際の支払い能力を伴った需要を有効需要という。今日の資本主義経済は、政府が経済に介入し調整を行う修正資本主義経済(混合経済)である。
このもとで政府は、例えば不況時には公共投資の拡大や減税などによって需要を創出して景気回復を図り、景気過熱時にはその逆の施策をとる。このように政府が積極的に経済に介入する政策を有効需要政策といい、これはケインズによって理論付けられた。
ニューディール政策
アメリカ大統領フランクリン=ローズベルトによって行われた世界恐慌の克服政策。
- 福祉国家的施策…テネシー川流域開発公社(TNA)法、全国産業復興法、全国労働関係法、社会保障法の制定など。労働基本権や社会権の具体的実現のための立法・施策が進んだ。
- 大きな政府…政府が経済や福祉に積極的に介入するさきがけになった。
マルクスの経済思想
資本主義経済を批判し、労働者の団結による革命により、社会主義社会を建設することを主張した。
- 資本主義批判・分析…マルクスは「資本論」の中で、資本家の得る剰余価値(利潤)は労働者からの労働価値の収奪の結果であるとした。また資本主義社会の詳額な分析・批判、共産主義革命の目的について述べた。
- マルクスとエンゲルス…1848年に「共産党宣言」を発表。「万目の労働者よ、団結せよ!」と述べてプロレタリア革命を唱えた。
- 科学的社会主義…エンゲルスは「空想から科学へ」で、マルクス・エンゲルスの社会主義思想を科学的社会主義と呼び、それまでの社会主義思想を空想的社会主義と呼んで区別した。
資本主義の矛盾を議会制度によって解消しようとする考え。
- ベルンシュタイン…労働者階級が中心となり、議会活動によって社会の改良を図ることを唱えた。主流派から修正主義と批判されることがある。
- フェビアン協会…1884年、イギリスで設立。議会を通して漸進的に社会主義を実現すべきことを主張した。
社会主義経済の成立
経済的平等を掲げ、経済体制を変革しようとする思想、資本主義経済の問題点を克服するものとして主張。生産手段の社会的所有労働帯への公平な分配を目指すことが目的、生産手段を私的に所有する資本家・地主は存在しない、労働力の高晶化や利潤の追状が起きず、公平に労働者に分配されると考えられた。
ソ連のコルホーズ、ソフホーズなどの農業の集団化や中国の人民公社などが顕著な例。計画経済・市場の自動調節機能による資源配分に任せず、政府が資源の配分をすべて計画する、このため景気変動はない。
- ソ連…1917年、ロシア革命。1922年、世界最初の社会主義国家、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が成立。
- 社会主義国の拡大…第二次世界大戦後、東欧や東アジア、キューバなどで成立。
社会主義国としてのソ連
計画経済や生産の非効率性、技術の発展の遅れから経済が停滞した。利潤道入方式を取り入れ、1980年代にはペレストロイカ(改革)を推進して経済の活性化を進めたが、失敗。1980年代から90年代にかけて、東欧諸国は市場経済に移行した。1991年にソ連は解体した。
社会主義国としての中国
社会主義を維持しながら、改革開放政策がとられ、市場経済の導入を進めている。
- 経済特区…外国資本を積極的に導入するため、中国南東沿岸部に設置。
- 社会主義体制下での市場経済…1990年代に急速に社会主義市場経済への移行が進む。近年、急激な経済成長を遂げ、世界第2位のGDPに成長。
- 一国二制度…香港・マカオでは社会主義と資本主義が共存して維持されている。特別な行政区として、大幅な自治権を有する。
- WTO加盟…2001年に加盟。2005年、人民元切り上げ。
社会主義国としてのベトナム
1980年代から、外国資本の導入と市場経済化をはかるドイモイ (刷新)政策を進め、経済成長を続ける。
新自由主義
ケインズ主義的政策で繁栄し豊かになった西側諸国だったが、経済成長しながらも財政赤字を増やしていったことから、市場機構を重視して小さな政府をめざす。新自由主義は、1970年代後半から台頭。
1973年のオイル・ショックで各国経済は打撃を受け、財政赤字は更に増大するようになった。とくに巨額の財政赤字を出すようになったアメリカは、スタグフレーション(注1)の状況にもなり、緊縮財政から財政健全化へと転換する必要が出てきた。
(注1)スタグフレーション
不況下でインフレが進む現象。先進諸国では賃金は下がりにくく(賃金の下方硬直性)、そのため雇用率は上がらずインフレが進んだ、石油などの一次産品の価格の上昇が先進国の賃金水準や福祉国家的政策と複合しておきることが多く、購買力の低下をもたらす。
フリードマンの主張
- 公共事業の停止…フリードマンは、公共事業を常用することは、インフレを押し上げ、かえって完全雇用を達成できないと主張。スタグフレーションや望ましくない景気変動を招いていると考えた。
- マネタリズム…貨幣供給量を経済成長率に合わせて一定に保つように提言。物価の安定に有効で、景気変動を抑えることができると主張。
新自由主義的施策
アメリカではレーガン大統領によるレーガノミクスが進められた。1970年代末に誕生したイギリスのサッチャー政権、緊縮財政、規制緩和、民営化、社会保障の削減などの新自由主義的政策を進め、サッチャリズムと呼ばれた。
日本の新自由主義
中曽根政権の下、三公社(日本電信電話公社、日本専売小社、国鉄)の民営化。小泉政権の下、特殊法人の廃止、郵政の民営化。

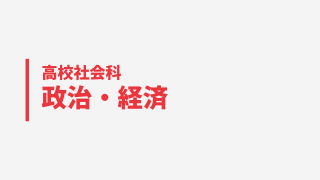
コメント