【高校政経】選挙制度とその課題・政治参加の要点です。
選挙制度の基本原則
- 普通選挙…人種・信条・性別・社会的身分・門地・財産および収入で有権者の資格を制限せず、成年者すべてに選挙権を与える選挙。→制限したものを制限選挙という。
- 平等選挙…選挙人の社会的身分や財産・納税額などで票の価値を差別せず、1票の価値の平等を保障する制度。
- 直接選挙…選挙人が候補者に対して直接投票を行う制度。アメリカ大統領選挙に見られる間接選挙に対比される。
- 秘密選挙…選挙人が無記名投票を行うこと。投票の自由を保障。
小選挙区制と大選挙区制
- 小選挙区制…各1つの選挙区から1人の候補者が当選する制度。
- 大選挙区制…1つの選挙区から複数の候補者が当選する制度。
小選挙区制メリット
- 二大政党制による政権の安定が得られる。
- 議員と選挙民との関係が密接になる。
- 選挙費用が比較的少額ですむ。
- 候補者の乱立を防止し、選挙の取り締まりが徹底しやすい。
大選挙区制メリット
- 小選挙区制よりも死票が少ない。
- 少数派でも代表を送ることが可能。
- 国民の意思が議会に公平に反映される。
- 国民の代表として有能な人物を選出できる。
小選举区制デメリット
- 死票が多く生じる。
- ゲリマンダーの危険性が大きい。
- 選挙干渉、買収などの不正が行われやすい。
- 少数党の進出をはばみ、全国民の代表者としての適格性を備えない地方的ボスが当選しやすい。
大選挙区制メリット
- 小党分立の傾向を強め、政局の不安定化を招きやすい。
- 選挙区が広いため多額の選挙費用が必要。
- 同一政党に属する候補者間の同士打ちを招きやすい。
- 補欠選挙などが行いにくい。
かつての選挙制度
日本では、かつて(1993年までの衆議院議員選挙で、1選挙区から3から5名を選出する中選挙区制を採用していた。これは大選挙区の一種で、その長所・短所の傾向も大選挙区制のものにあてはまるが、極端な小党分立になることはなかった。
公職選挙法
1950年に制定。選挙権、被選挙権、選挙区, 投票方法、選挙運動。選挙管理などを定めた公職の選挙に関する総合的な基本法。
選挙権
満18歳以上のすべての男女。
被選挙権
- 衆議院議員・地方議会議員・市町村長→満25歳以上。
- 参議院議員・都道府県知事→満30歳以上。
選挙事務の管理
選挙管理委員会が担当している。
- 中央選挙管理会…比例代表制議員の選挙、最高裁裁判官の国民審査を扱う。
- 都道府県選挙管理委員会…衆議院小選挙区・参議院選挙区・地方議会の議員・都道府県知事の選挙。
- 市町村選挙管理委員会…市町村長と地方議会議員の選挙を扱う。
投票の方法
公職選挙法によると直接選挙制、投票用紙の公給制、本人出頭制、投票自書制、一人一票制、単記投票制、無記名制が規定されている。ただし、例外的に不在者投票や代理投票、点字投票が認められている。
選挙権の拡大
| 選挙法の公布・改正の年 | 有権者の資格 | 人口に対する割合 |
|---|---|---|
| 1889年衆議院議員選挙法公布 | 直接国税15円以上を納める25歳以上の男子 | 1.1% |
| 1900年衆議院議員選挙法改正 | 直接国税10円以上を納める25歳以上の男子 | 2.2% |
| 1919年衆議院議員選挙法改正 | 直接国税3円以上を納める25歳以上の男子 | 5.5% |
| 1925年衆議院議員選挙法改正 | 25歳以上の男子(納税条件の撤廃) | 20.0% |
| 1945年衆議院議員選挙法改正 | 20歳以上の男子および女子 | 48.7% |
| 1950年公職選挙法公布 | 20歳以上の男子および女子 | 54.5% |
| 2015年公職選挙法改正 | 満18歳以上の男女 | 80% |
衆議院議員選挙制度の改正
1994年に中選挙区制をやめて、小挙区比例代表並立制がとり入れられた。これは、全国を300の小選挙区と拘束名簿式の11のブロックか180人を選出する比例代表区に分けて選挙を行うもので、これにより、候補者は小選挙区と比例代表区に重複立候補できるようになった。2013年以降の選挙では、小選挙区の定数は295人となる。
参議院議員選挙制度の改正
2000年の公職選挙法の改正により、現在は都道府県を単位に146人を選出する選挙区選出制と全国を単位として96人を選出する非拘束名簿式比例代表制の並立となった。非拘束名簿式では有権者は、各政党の立候補者個人名または政党名を記入して投票する。その合計が各政党の得票数として議席が配分され、個人名の得票が多い順に当選となる。
日本の選挙の課題
議員定数不均衡
選挙区によって、議員1人あたりの有権者数が大きく異なるため、選挙区ごとの一票の格差が問題となっている。これまでは、最高裁は衆議院議員選挙で3倍、参議院議員選挙で6倍の格差を「違憲」と判断してきた。
- 衆議院議員選挙の一票の格差…2011年3月、最高裁で衆議院議員選挙の最大2.30倍の格差は「違憲状態」(早急な立法措置を求める)と判断した。
- 参議院議員選挙の一票の格差…最高裁は2012年10月、5.00倍の格差は「違憲状態」と判断した。
選挙活動の規制の問題
- 連座制…候補者と特定の関係にある者が選挙違反をした場合、候補者自身が関与しなくても当選を無効にする制度。候補者は選挙協力者に責任をおしつけ、公職選挙法違反の疑いがありながら当選する状況が背景にあった。
- 戸別訪問…各家庭を訪問して投票を依頼すること。日本では買収が心配され、禁止。表現の自由の観点から戸別訪問の禁止条件を緩和すべきという意見もある。
投票率の低下
長期的には国民の政党離れ、政治不信で低下傾向にある。
制度の改革
選挙権年齢18歳への引き下げ、永住外国人の参政権などが議論の対象となる。また、2013年7月の参院選から、ネットでの選挙活動が解禁された。
政治的無関心
政治意識の多様化や価値観の複雑化によって、投票率の低下や政治離れが増加している。このため、国民による政治へのチェックが甘くなり、民主主義的な政治が行われない危険が生じている。
政治的無関心のタイプ
- 伝統型無関心…政治に対する無知や権威に対する盲従から生じる無関心。
- 現代型無関心…大衆社会において、個人の関心の多様化や娯楽、マイホーム主義などのために政治に対して著しく消極的で受動的になっている無関心。
現代型無関心のタイプ
アメリカの政治学者ラスウェルは、現代型の政治的無関心のタイプを次の3つに分類した。
- 無政治的態度…政治についての関心や一般的知識が乏しく、政治は自分以外のだれかが行う仕事だと考える。政治的無関心の一番多いタイプ。
- 脱政治的態度…政治や政治家に強い幻滅や絶望感を抱き、政治との関わりを積極的に避ける。選挙に際しても、だれが当選しても同じとして棄権する。
- 反政治的態度…自分の考える政治的価値や宗教的価値観と政治的権力とは相入れないとして、政治家・政党・官僚などに対し積極的な反発・非難や存在価値の否定などを行うタイプ。個人的無政府主義者に多くみられる。
無党派層の増加
日本では有権者と政党との結びつきが希薄である。さらに 政党の度重なる公約違反や腐敗、離合集散などにより、政党への反感・不信感が 増加している。このため、政治に関心をもちながらも特定の政党を支持しない層が高い割合を占めるようになって、選挙結果を左右する力をもつようになった。
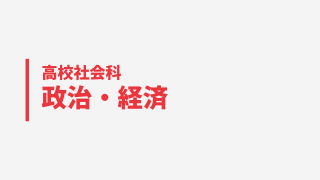
コメント