【高校政治経済】戦後の政治についてまとめています。
戦後の政党政治
第二次世界大戦後の民主化政策により、政治活動の自由が認められ、政党の再発足や新党の離合集散が1948年ごろまで続いた。
55年体制と保守政権の時代
1955年に左右に分裂していた日本社会党が再統一し、これに対抗して保守勢力が合同して自由民主党(自民党)が成立。この体制は55年体制と呼ばれた。実際には社会党は自民党の半数の議席しかなく1と2分の1政党制といわれ、自民党による長期政権が続いた。
多党化の時代
野党を中心にして新政党が生まれた。1960年、社会党から民主社会党(民社党)が分立。また1964年、公明党が成立。1976年、新自由クラブが自民党から分立した。1983年に新自由クラブは中曽根内閣の下で自民党と連立し、1986年には自民党に再合流した。
55年体制の崩壊
ロッキード事件、リクルート事件、佐川急便事件など、金権汚職事件が発生して、政治腐敗が大きな問題となり、政治改革の動きの中で保守系の新政党が相次いで結成された。1993年、保守合同以来38年ぶりに政権が交代し、非自民・非共産の連立政権による細川内閣が誕生した。
自社連合から自公連立へ
1994年、村山内閣が誕生。自民、社会、新党さきがけによる連立政権であった。その後、1998年に自民党は社会党さきがけとの連立解消。1999年に自公連立政権(この時点では自民党、公明党、保守 党の自公保連立政権)に移行した。
小泉内閣と構造改革
2001年、自公連立で第1次小泉内閣が誕生し、高支持率を背景に市場原理を重視した構造改革と呼ばれる一連の改革に着手。第2次小泉内閣は2005年、衆議院選挙で大勝し、郵政民営化を推進した。小泉政権は戦後歴代3位の長期政権となり、その後も安倍・福田・麻生内閣と続いた。→自公連立も継続
民主党政権
2009年、衆議院総選挙で民主党が第一党となり、政権交代が実現して、鳩山内閣が誕生した。しかし、民主党政権は普天間基地移設問題など
で支持率を失い, 2010年の参院選で惨敗した。このため衆議院では与党の自民党が、参議院では野党が多数となるねじれ国会と呼ばれる状況となった。鳩山内閣の後の菅・野田内閣も東日本大震災や原発問題などで批判を浴びた。
第2次安倍政権
2012年12月の衆議院議員選挙で民主党は大敗し、自公連立の第2次安倍政権が誕生した。
政党政治の課題
日本の政党は、国民の中にしめる党員数の割合が低く、国民全体の利益を代表することを標榜する国民政党としての性格が乏しい。また政 党は、党全体では圧力団体や財界、宗教団体、労働組合などによる組織票・政治資金に依存している。改革の妨げとなり、政党がしばしば迷走する原因となる。
派閥の形成
保守政党も革新政党も、政策論争やイデオロギーの対立、あるいは資金源の違いで派閥がつくられており、政策よりも派閥間の力関係・利益を優先させる傾向が強い。こうした傾向は派閥の論理と俗称されることがある。
族議員の誕生
官庁と圧力団体・業界との間に立って利益調整を行う族議員が大きな力を持つようになった。道路族・建設族・農林族などと呼ばれる。
政治資金の収支の明確化
政党は、圧力団体や個人から寄付や献金 を得て政治活動を行うことが多く、政治腐敗に結びつくことがある。このため、政治資金規正法により公正な資金調達を確立し、健全な政党活動の確保をめざしている。1994年成立の政党助成法によって、政党交付金として公費で政党活動を助成することになった。
党議拘束
議会での採決に際し、所属政党の方針に従って投票するように議員を拘束する。議員の自由な発言や議論が疎外されているという批判がある。
無党派層の増加
政治不信から、無党派層が激増。政治的無関心とは違い、政治に関心はあるが決まった支持政党をもたない。無党派層の投票動向は選挙の 行方を大きく左右する。国民の信頼を回復させるための努力が求められている。
政党政治
政権獲得を目標とする政治集団。
- 政党の発生…イギリスで17世紀後半に誕生したトーリー党とホイップ党が議会政治における最初の政党とされる。制限選挙下での名望家政党(院内政党)であった。選挙制度の民主化、普通選挙のはじまりに伴い、名望家政党から大衆政党(組織政党)へ発展。
- 政党…イギリスのバークは、「ある特定の主義または原則において一致している人々が、その主義または原則に基づいて国民的利益を増進すべく協力するために結成した団体」と定義した。政党をはじめて公党と認めた点で重要。
政党による政治活動
政党は、他の社会集団と異なり、政党の公約 や基本方針を掲げた綱領をもつ。選挙の際に掲げられる選挙公約や政権公約をまとめたものはマニフェストという。政党は、国民の代表機関である議会を通して政策立案を行い,特定の主義・主張・政策の実現を図る。
政党の役割
政党は政治と世論の連結機と表現される。また、多様な意見を反映するチャンネルとも呼ばれる。政権を担当している政党を与党政権を担 当しない政党を野党という。
圧力団体
利益団体(利益集団)とも呼ばれる。集団の特殊利益の実現を目指す集団で、議会や政府に働きかける。正常な議会の審議をさまたげることもある。アメリカでは、19世紀末から20世紀初めにかけて台頭してきた。
ロビイスト
アメリカでの圧力団体の代理人。議会室外の広間(ロビー)で送動することからこう呼ばれる。
族議員
特殊利益を実現するための代弁者として、一部の業界等と強く結びつき、政策に影響を与える。特定企業との癒着がおこり問題となる場合がある。
二大政党制
- 単独政権になりやすい。
- 政局が安定しやすい。
- 政策上の争点や責任の所在が明確。
- 少数者の意見が反映されにくい。
イギリス・保守党と労働党やアメリカ:共和党と民主党がその代表例
多党制
- 連立政権になりやすい。
- 政局が不安定になりやすい。
- 国民の多様な意見を反映させやすい。
- 少数政党が政治の主導権(キャスティング・ボート)を握ることもある。
フランス、ドイツ、日本など。一党優位体制や、実質的には一党制となる開発独裁なども含まれる。
一党制
- 独裁となり、世論は無視され、政策が硬直化する。
- 政治腐敗が起こりやすい。
社会主義国は、キューバなど。
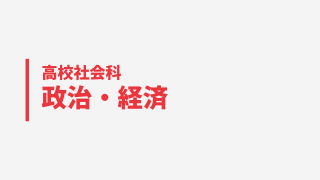
コメント