【高校政治経済】国際紛争の要点ポイントです。
国際紛争の要因
- 政治的要因…国益を追求する国家間の利害の対立。
- 経済的要因…豊かな国と貧しい国との間の経済格差。
- 社会的・文化的要因…人種・民族・宗教・イデオロギーなどの相違。
冷戦期の紛争
冷戦中は米ソが絡む紛争、代理戦争が世界各地で頻発。武力を伴う紛争に発展しやすい。
- フォークランド紛争…1982年、イギリス・アルゼンチン間でフォークランド諸島帰属問題を巡り、勃発。
- スプラトリー諸島問題…中国・ベトナム間でスプラトリー島を巡って起きた衝突。
冷戦後の主な武力紛争要
- ソマリア内戦…国連は軍事力を用いた第2次国連ソマリア活動(UNOSOMⅡ)を展開したが,平和創設に失敗して撤退。
- ルワンダ内戦…フツ族 ツチ族間の内戦。
- ダルフール紛争…スーダン西部で続く,反政府軍との衝突、内戦。
- チェチェン紛争…独立を求めるチェチェン共和国とロシアとの間の紛争。
- 南オセチア紛争…グルジアから独立を求める親ロシアの南オセチア地域の紛争。グルジアとロシアの武力衝突に発展。
- 東ティモール前争…インドネシアからの独立を求めて起きた紛争。国連東ティモール・ミッションによる監視下の住民投票。2002年、独立。 カシミール紛争…今なお続くインド・パキスタンによる紛争。
- パレスチナ紛争…イスラエルとPLO(パレスチナ解放機構)の間でテロや衝突、報復攻撃が続く。
民族問題
- 公民権運動…アメリカで1950 ~ 60年代に黒人の地位向上を目指した運動。
- アパルトヘイト(人種隔離政策)… 南アフリカ共和国では、自人の黒人に対する激しい差別政策が続いていたが、1991年に廃止された。
- エスノセントリズム…自民族中心主義。人種・民族問題の根幹。

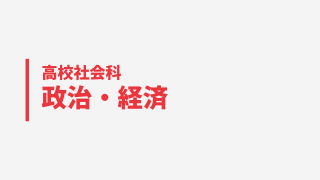
コメント