【高校政治経済】経済主体と経済循環のポイントです。
経済主体
経済活動に参加する単位として、次の3つの経済主体がある。
1.家計
所得と消費財・サービスを消費する経済主体。同時に企業や政府に対して労働力を提供し、賃金(労働所得)を得る。効用(消費)により得られる満足の度合いの最大化をめざす。
- 可処分所得…家計の得た所得のうち,租税や社会保険料などを除いたもの。 可処分所得は消費に割り当てられ、残りは貯蓄される。
可処分所得=所得-(租税+社会保険料)=消費支出+貯蓄
可処分所得に対する消費支出の割合を平均消費性向という。
- エンゲル係数…家計の消費支出に占める食料費の割合。所得が高くなるほどエンゲル係数は低くなる傾向がある。生活水準をはかる指標の1つ。
2.企業
資本の提供を受けて労働者を雇用し,生産財の購入などの設備投資を行い、財・サービスの生産を行う。
- 生産活動の主体…財・サービスを生産し,市場で販売する経済主体。企業の目的は、利潤の最大化である(営利活動)。
利潤=総売上額-費用(労働者の賃金+原材料費)
企業の種類は、国や地方公共団体が出資し、経営する公企業、民間の出資・経営による私企業、政府と民間の共同出資による公私合同企業に大別される。 私企業の代表としては株式会社がある。
3.政府
家計・企業から租税と社会保険料を徴収し、公共事業などにより公共財を社会資本(インフラストラクチャー)として整備し、警察・消防・教育・ 医療などの公共サービスを提供する。また社会保障給付を行う。
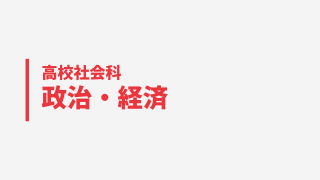
コメント