【高校生物基礎】生命の誕生と進化のしくみについてまとめています。
生命の起源
地球の誕生は、約46億年前、微惑星の衝突によって形成された。
自然発生説
「泥からウナギが生まれる」などの、生物は無生物から自然に発生するという考え。レディやバスツールにより否定された。
化学進化説
「原始地球上において生命が発生する条件がそろい、無機物から有機物ができ、長い時間をかけて化学反応によって生命が誕生するための材料が生成した」という最初の生命発生に関する説。
ミラーの実験
当時原始大気と考えられ ていたCH4(メタン)・NH3(アンモニア)・H2O(水)・H2(水素)から放電や熱による化学反応でアミノ酸ができることを確かめた。(現在では原始大気の主成分はCO2,N2, H2O,COなどと考えられている。)
原始生物へ
原始の海の有機物(アミノ酸・塩基・糖・核酸など)が膜様物質に包まれて独立した代謝・自己増殖などを行う生命体となったとする。コアセルベート説(オパーリン)、RNAワールド説などが有力。海底の熱水噴出孔が生命誕生の場として注目されている。
原始生物の誕生
約40~38億年前、原始的な細菌類の誕生。有機物をとり込んで嫌気呼吸をする従属栄養生物の細菌とメタン・水素・硫黄などを酸化させてエネルギーを得る独立栄養生物の化学合成細菌。最古の化石は、約35億年前の細菌の化石。オーストラリアの地層から。
進化のしくみ
進化論は、19世紀、生物は進化するという考えが生まれる。
用不用説と自然選択説
- 用不用説…ラマルク(『動物哲学』1809年)。生活の中でよく使う器官は発達し、使わない器官は退化するという説。獲得形質は遺伝しないことから現代では否定的。
- 自然選択説…ダーウィン(『種の起源』1859年)。食物や空間をめぐる生存競争と適者生存により変異が積み重ねられるという説。
突然変異と進化説
- 突然変異説…ドフリースが突然変異を発見し、提唱した説。(1901年)。「進化のもとになる変化は環境の影響とは無関係」
- 中立説…木村資生が提唱。「突然変異の多くは自然選択にとって有利でも不利でもない」
現在の進化学
化石研究に加え, 集団遺伝学や分子進化学・社会生物学などから進化を多角的に研究。DNAレベルの突然変異が自然選択や遺伝的浮動、隔離などによって種分化に発展すると考えられている。
突然変異
生殖細胞に起こった突然変異は次世代に遺伝する。突然変異には遺伝子突然変異と染色体突然変異がある。
自然選択(自然淘汰)
集団内の突然変異が生存に有利な形質である場合、遺伝して世代を重ねるごとにその遺伝子を持つ個体が集団全体に増える。
- (例)工業暗化…イギリスの工業地帯で樹皮の暗 黒化(大気汚染で地衣類が死滅)→オオシモフリエダシャク(ガの一種)が、目立って鳥に捕食されやすい淡色型から黒色型中心に。
遺伝的浮動(機会的浮動)
集団が小さいと,有利でも不利でもない形質が偶然に選択され,遺伝子頻度が増加することがある。
隔離
地理的あるいは生殖的に隔離が起こることで種分化が進む。
- 地理的隔離…地形の変動により海や山などで分断された集団で個別に突然変異や自然選択による変化が進む。(ワーグナー)
- 生殖的隔離…隔離された集団の間で生殖器官の構造や生殖時期に違いが生じ、集団間の交配ができなくなる。(ロマニーズ)

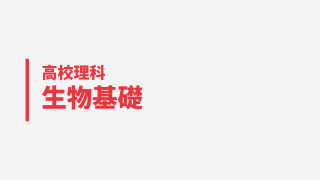
コメント