【高校生物】種子の発芽と調節についてまとめています。
種子の発芽と調節
多くの植物では種子が形成されるこの休眠状態になります。休眠状態の種子は水・温度・酸素といった環境条件が整い、かつアブシジン酸の減少やジベレリンの増加といった種子内の条件が整うと発芽します。
光発芽種子
レタスやタバコの種子のように光を照射することで初めて発芽できる種子を光発芽種子といいます。逆に、強い光によって発芽が抑制される種子もあり、暗発芽種子といいます。暗発芽種子の例にはカボチャ・ケイトウなどがあります。
吸水させたレタスの種子の光発芽実験
- ずっと暗所に置く→発芽しない
- ずっと明所に置→発芽する
- R照射→暗所に置く→発芽する
- R照射→FR照射→暗所に置く→発芽しない。
- R照射→FR照射→R照射場→暗所に置く→発芽する
- R照射FR照射→R照射→FR照射→暗所に置く→発芽しない
Rは赤色光、FRは遠赤色光
実験からわかること
3の結果から赤色光を照射することで発芽できることがわかります。つまり、赤色光が発芽促進に有効だということです。しかし、4では発芽しません。遠赤色光の照射が赤色光の効果を打ち消してしまったのです。逆に、6では赤色光照射が遠赤色光の効果を打ち消して発芽しました。つまり、最後に赤色光と遠赤色光のどちらが照射されたかによって、発芽できるかどうかが決まるのです
2の現象には種子内にあるタンパク質が重要だとわかっています。このタンパク質は赤色光によって発芽を促進するタイプに変化します。しかし、遠赤色光によってもとにもどってしまいます。
オオムギ種子発芽
胚が合成したジベレリンが種子の糊紛層に作用し、そこからアミラーゼが合成されます。アミラーゼが胚乳に貯蔵されていたデンプンを分解し、分解産物のマルトースやグルコースを胚が利用して発芽します。
- アミラーゼ…だ液に含まれ、炭水化物(デンプン)を消化します。
- ペプシン…胃液に含まれ、タンパク質を消化します。
- トリプシン、リパーゼ…どちらもすい液に含まれ、トリプシンはタンパク質、リパーゼは脂肪を消化する。
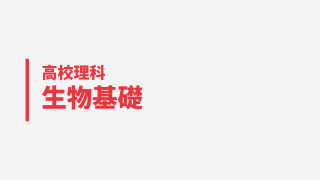
コメント