【高校倫理】和辻哲郎の思想についてまとめています。和辻哲郎(1889年から1960年没)は、東京帝国大学で哲学を学んだ後、夏目漱石と出会い、影響を受けた。和辻哲郎は初め、ニーチェやキルケゴールを研究した。西田幾多郎の招きで京都帝国大学に在職中、ドイツに留学してハイデガーの哲学に触れた。
和辻哲郎の著書
- 人間の学としての倫理学
- 古寺巡礼
- 風土
和辻哲郎は、ドイツ留学からの帰国後の1934年、『人間の学としての倫理学』を発表した。 西田幾多郎の影響も受けながら、西洋思想を批判的に受容して 独創的かつ日本的な倫理学を構築した。
倫理学のほかの分野でも幅広く業績を残し、『古寺巡礼』では奈良近辺の古寺の建築や仏像を芸術論や文化史の対象としてとらえ直した。
また、『風土』では風土とそこに生きる人間存在のあり方との深いかかわりを論じた。
間柄的存在
『人間の学としての倫理学』において、和辻哲郎は、人間存在のあり方を、独立した個人としてではなく間柄的存在としてとらえた。日本語の人間は「人の間」と書くように、単に個人を表すものではなく、人と人との「間柄」 をも示している。間柄的存在とは、このように他者との関係性において人間存在をとらえることをいう。
人間の学としての倫理学
和辻哲郎は、「人間」には個人的存在と社会的存在という2つの側面がある。しかし西洋近代の倫理学は、倫理を単に個人意識と見ていると和辻哲郎は批判する。
倫理は、単に個人だけの問題でも社会だけの問題でもなく、人と人との間柄の問題であり、個人と社会との相互作用において成立する。倫理をこのようなものとしてとらえる倫理学を、和辻哲郎は「人間の学としての倫理学」と呼んだ。
個人と社会
個人は社会の中での個人であり、社会を離れた孤立した存在ではない。同時に、社会は個々人があって成り立つものであり、個人を離れた社会は存在しない。
そこで、倫理的な生き方の根本は、人間が社会に埋没せず、社会に解消できない個人としての自己を自覚するとともに、その自己を否定して、社会ために生きるという動的な関係の中に求められるという。
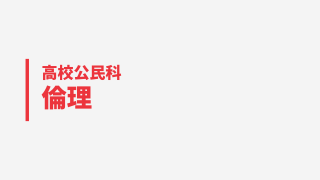
コメント