【高校倫理】アリストテレスの思想についてまとめています。アリストテレス(前384年から前322年没)は、はじめプラトンの学園アカデメイアで20年学んだ。マケドニア王に招かれて、後のアレクサンドロス大王の教育にもあたった。やがてアテネに戻り、自らの学園リュケイオンを開いた。アリストテレスは、師のイデア論を批判し、哲学・政治学・天文学・生物学など多方面の業績を残し、万学の祖といわれる。
- イデア論…プラトンはイデアを理性(精神) によって観られた、理想の形や本質という意味で用いた。
確認【高校世界史】ギリシア文化のまとめ
イデア論批判とは、
その➊理想主義と現実主義の違い
プラトンは現象界を超えたイデア界を重視し、現実の事物ではなく、イデアこそ真実在であるとする理想主義の立場をとった。しかし、アリストテレスは現実主義の立場をとり、現実世界における個々の事物(個物)こそ実在であるとして、その変化や運動を説明しようとした。
その➋形相と質料における批判
アリストテレスの考えでは、個物は、それが「何であるか」を示す本質=形相(エイドス) と、それが「何でできているか」を示す素材=質料 (ヒュレー)からなる。たとえば、木の箸は「箸」という形相と、木材という質料からなっている。形相は、プラトンのいうイデアに相当するが、個物を超えて存在するのではなく、個物に内在しているとした。
その➌可能態と現実態
アリストテレスは、「木材という質料の中に著という形相が可能性として含まれている。」と考えた。職人が木材から箸を作ることで、その可能性は現実化され、箸の形相が具体的な姿をあらわす。ここで、形相が質料の中でまだ可能性にとどまった無規定な状態のことを可能態とよび、形相が実際に姿をあらわし、現実化された状態 (先の例では完成された著)のことを現実態とよんだ。アリストテレスは、たとえば樫の実(可能態)が樫の木(現実態)になるように、「あらゆる運動や変化は自らのうちに可能性として含まれる形相を目的としている。」とした。
最高善とは
アリストテレスは、幸福こそ人生の最終目標であり、最高善とした。
固有の機能と幸福
幸福とは、そのものが持つ固有の機能(そのものをそのものたらしめる働き)を十分に発揮することだと、アリストテレスは考えた。例えば、鳥が固有に持つ機能は「飛ぶこと」であり、鳥にとっての幸福な状態とは「自由に飛んでいる」状態。
人間の幸福
アリストテレスによれば、人間にとって固有の機能、人間を人間たらしめるものとは理性である。そこで、理性を十分に働かせた活動こそ人間にとって最高の幸福(最高善)だとした。
観想的生活
アリストテレスは、他の目的のためでなく、純粋に真理を認識するために理性を働かせる観想的生活(テオリア的生活)こそ、人間にとって最高に幸福な生活であるとした。
知性的徳と倫理的徳
アリストテレスは、人間が観想的生活を送るためには、徳がなければならないと考えた。そして、徳を知性的徳と倫理的徳に分けた。
知性的徳とは
魂の理性的部分の働きから生じるのが知性的徳である。真理を認識 する理論知である知恵や、行為の適切さを判断する実践知である思慮などが含 まれる。知性的徳の修得には教育や学習 を必要とする。知恵によって最高の幸福 ある観想的生活を送ることができる。
倫理的徳(習性的徳)とは
感情や欲望は、それ自体では過度や不足の両極端に陥りがちである。倫理的徳を身につけるには、知性的徳の思慮(フロネーシス)の導きにより、常に両極端を避けた中庸を選択するよう日常生活の中でくり返し、習慣づけをしなければならない。習慣(エトス)により身につく徳なので、習性的徳とも呼ばれる。
以上が、【高校倫理】アリストテレスの思想のポイントとなります。
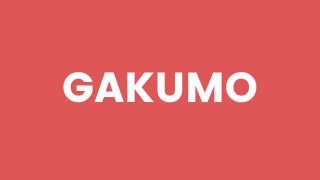
コメント