今回は、「異文化理解」についてです。
【問題】日本は異文化をどのように取り入れ、発展させてきたか、あなたの考えを述べよ。(600字)
異文化理解の解答例
日本人は、異なる文化を積極的に取り入れ高い水準まで発展させている。なぜならば日本人の性格が関係していると考えられる。日本人は、一つのことを丁寧にこなし、職人のようなこだわりを、持っているのだ。カレーとデニムの例から考察する。
もともとインドやイギリスで食べられていたカレーは、明治時代に日本に入ってきた。イギリスのカレーは、カレー粉を用いて作られていたり、インドのカレーは、液体状になっていたりと、各国によって見た目や味は多種多様であった。その中で日本は、日本人の好みに合わせて、とろみのあるカレーを開発したのだ。このように、日本人は職人としての気質を持ち、人によって異なる食の好みに合わせ発展しているのだ。
一方で、デニムの例では、日本人は、古くから着物で生活をしている文化があったが、アメリカの文化が日本に入ってくることによって現在では、デニムを履く人は増加してきている。そこで、日本の文化である着物を着る人が減少してしまうことを懸念し、日本の着物を作る会社は、身近に着物に慣れ親しんでもらうために、デニム素材を使用した着物を販売している会社も出てきている。
このように、日本では異文化を積極的に取り入れつつ、人々の嗜好に合った形で食や文化を発展させてきているのだ。
異文化理解の解答に対しての講評(一部抜粋)
論文は、異文化の取り入れと日本の発展について興味深い洞察を提供しています。明治時代のカレーとデニムの例は具体的で分かりやすく、日本人の職人気質が文化発展にどのように寄与しているかを示しています。ただし、もう少し深い分析や異文化取り入れの社会的・歴史的背景に触れるとより充実した論文になるでしょう。
異文化理解の解答に対しての添削
(原文)日本人は、異なる文化を積極的に取り入れ高い水準まで発展させている。なぜならば日本人の性格が関係していると考えられる。日本人は、一つのことを丁寧にこなし、職人のようなこだわりを、持っているのだ。
→日本人は、一つのことを丁寧にこなし、職人のようなこだわりのある性格を持っている。それが異なる文化を積極的に取り入れることにつながるのだろうか? ちょっと強引というか、因果はないですね。「平均寿命は伸びている。それはテレビが普及したからだ。テレビを観て、笑うことが増えたのだ。」この例と同じです。因果関係はあるようで、違いますよね。
因果関係を考えるときの材料
・実験結果などエビデンス(根拠・証拠)があればそれに基づいたものにする
・歴史的事実
・地理的、政治的、経済的視点
・当事者意識(当事者になってみる)
など視点を広げることで、説得力のある理由につなげていきましょう。
<例>
日本人は異なる文化を熱心に受け入れ、それを丁寧かつ独自の視点で発展させている。この特徴は、職人のようなこだわりと一つのことに真摯に向き合う性格に起因していると考えられる。カレーとデニムの例を通じ、日本は異文化を自らの嗜好に調和させ、その発展を見せている。しかしながら、さらに深い歴史的背景や異文化がもたらす社会的変化に触れることで、このプロセスがより理解されるだろう。結果的に、異文化を取り入れつつも、日本は独自のアイデンティティを守りながら食や文化を進化させてきた。
地理的条件と政治的条件
今回の場合の一般的な例として、「地理的条件」と「政治的条件」の背景(視点)が大事になってきます。
【地理的条件】島国であり、かつ江戸時代には鎖国もしていたこともあって、外国(海外)の文化を取り入れる機会がなく、日本は独自の文化を発展させていった。(歌舞伎や能、絵画、和服など)
【政治的条件】それが、ペリー来航をきっかけに、開国することで、否が応でも、外国の文化が入ってきた。欧米(インドも含む。その当時、イギリスの植民地)諸国は、自分たちの物を日本に輸入することで儲けた(経済を発展させ、その利益で軍事力を強化。世界大戦などへつながっていく。)。日本は、自国より進んだ技術や文化にびっくりする。このままでは、外国に飲み込まれてしまう(植民地になる)ということで、国をあげて、軍事、文化が急速に発展させていった。
→以上のような背景を簡潔に述べて、文化を発展させることが、日本が生き残る手段だったとして、その中で、職人も育ち、改良・改善を重ね、日本人の嗜好に合った形で食や文化を発展させることにつながったのだというようなことが記述できると説得力は増しますね。
余談ですが、これが経済の発展にもこのことは言えて、資源に乏しい日本は、加工貿易で発展しましたね。
「日本は資源がとぼしく、原油などの燃料資源や工業原料などの大部分を海外から輸入して、それを加工・製品化して輸出する加工貿易を得意として経済成長」→これまであった物(文化・経済・政治など)に手を加えて、改良・進化させることが得意なのが日本と言われていた。身近にあるものの例でいえば、家電製品や自動車がその最たる例。どんどん改良・進化させてきました。
高度経済成長期には、ジャパン・アズ・ナンバーワンと呼ばれるほどに、日本製品は、世界最高の安全・安心の品質の証となりました。バブル崩壊後の失われた30年(平成元年以降)、日本は衰退の一途をたどっていますが…。
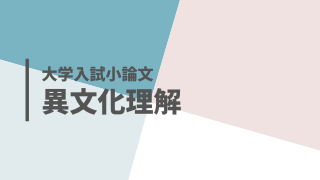
コメント