【大学入試小論文】関西大学文学部総合人文学科(2022年度AO入試)の小論文解答例です。改題となります。
【問題】朝日新聞EduAウェブサイト(2021年3月1日)から、日本の部活動の特徴について述べた文章と、Yahoo!JAPANニュース(個人記事、2018年12月26日)から、日本の運動部活動の問題点について述べた文章を読み、「大学での理想的な課外活動のあり方」について述べよ。
【改題】中高生の「部活動」の是非について、あなたの考えを1000字以内で述べなさい。
部活動の是非に関する解答例
私は学校に部活動の制度はなくなるべきだと思う。理由は二つある。
一つ目の理由は、部活動は教師への負担が重すぎるからである。教師は部活動の顧問を平日休日問わずしたとしても、それに見合う手当てはもらえない。また、担当する部活動の経験があるかどうか関係ないことは、教師にも生徒にも負担がある。
例えば、私は中学校の頃ソフトテニス部だったが、顧問の先生は全くの初心者だった。そのため、技術的な指導はなく、部員からは不満の声もあった。一方で、顧問は一からルールを勉強し、専用のシューズやラケットは自費で買っていた。半ばボランティアにも関わらず責任も重くのしかかるようなことを、進んでやってくれる先生もいるが、負担になる先生もいる。
また、教師の負担が重すぎるため、教師が顧問をすることは他にも影響かでる、教師には授業の準備や成績処理などやる事が多く、部活内の雰囲気やいじめの有無にまで、目が回らない。また、顧問がいないときに、命に関わる大きな事故が起きているのも事実である。よって、教師は顧問以外にも、通常業務があるため、そこまで手が回らないのは当然で、部活動の顧問を半ば強制的にさせるのは、やめるべきだ。
二つ目の理由は、学校では生徒が必ずしも、本当にやりたいスポーツや文化活動をできるわけではないからだ。私自身、高校で友達とチアダンス部を新しく作りたいという話になり、先生にその話を持ちかけた事がある。自分達でチアダンスの先生を見つける必要があったり、部員を集める事ができず、断念した。このように、生徒の望む部活動があるとは限らなく、また、新しく作ることはそう簡単ではない。
さらに、やりたい部活動がない生徒もいるにも関わらず、生徒を半ば強制的に部活動に参加されることは、部員間での温度さや対立がうまれ、ほんとにやりたくて入った人も、どちらの人も、本当に心から部活動を楽しめないと考える。
確かに、部活動は協調心を高め、最高の思い出や楽しさを生徒に提供してくれるかもしれない。だが、この役割は、学校外部のクラブチームも果たせると考える。つまり、本当にやりたいわけではないのに入る部活動や、生徒の温度がある部活動よりも、指導者がプロで積極性のある仲間がいる所で活動した方がより一層楽しめるわけだ。
以上のことより、学校の部活の制度はなくし、その代わり外部クラブチームを充実させていくべきだと考える。
部活動の是非に関する小論文講評(抜粋)
論文は熟慮された立論と具体例を用い、部活動の廃止を支持する主張を展開しています。特に、教師への負担や生徒が本当に望む活動が制約される点に焦点を当て、その背後にある問題点を明確に指摘しています。
【改善点】
具体的な事例やデータを引用して論文を強化することができるでしょう。また、外部クラブチームの具体的な利点や成功事例に触れることで、提案がより説得力を持つでしょう。最後に、反対の意見や部活動の利点にも簡潔に触れ、対話的なアプローチを取ることができると良いでしょう。
部活動の是非に関する小論文添削(抜粋)
さらに上のレベルを目指すということになれば、特に自分が詳しく知っている領域・分野であれば、「視点」を増やすということをこころがけましょう。
たとえば、今回の課題でいえば、
- 「海外の事例はどうなのか。(海外の視点)」
- 「部活動ができた背景・目的(歴史的な視点)」
- 「子どもや親(当事者の視点)」
- 「部活動の賛否などに関するデータや資料(客観的な視点)」
など。
【添削1】
✕(原文)自分達でチアダンスの先生を見つける必要があったり、部員を集める事ができず、断念した。
〇(修正)自分達でチアダンスの先生を見つけることや部員を集めることができず、断念した。
➨「~たり、~たり」は連続して使用しましょう。今回は、「~事、~事」としたほうがいいのかな。
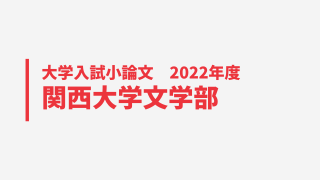
コメント