【大学入試小論文】持続可能な社会実現についての解答例です。
(A)我々の生活を便利で豊かなものにしてくれる高性能・高機能な製品や材料の開発は、結果的に資源エネルギーの節約や環境負荷軽減につながる場合が多いので今後も高性能な製品や材料の開発を続けていくべきである。
(B)必要以上の高性能化や高機能化を追い求めるよりも、生産工程の改良や製品のリサイクル(再資源化)などの環境技術開発をもっと進めていく方が資源やエネルギーの節約と環境負荷の軽減に寄与するはずである。
(A)の意見も(B)の意見も「環境にやさしい循環型社会」「持続可能な社会」の実現を意識した考え方といえる。上記2つの製品開発の進め方のメリットとデメリットをそれぞれ客観的に説明した上であなた自身の意見や考え方について述べなさい。(800字以内で記述すること)
持続可能な社会実現についての解答例
(A)のメリットは、開発後に永続的に環境問題に有効であり、まだ未開発の分野や材料も多く残っているため無限の可能性があることだ。一方で、デメリットはコストがかかり、開発に数十年の時間を要することだ。その上、その開発中に環境に負荷をかける可能性がある。
(B)のメリットは、既にある製品の改良やリサイクルであるため、(A)に比べて開発に時間がかからない。さらに環境負荷の根本的な解決に繋がる。しかし、改良やリサイクルには限界があり、処理しきれない有害物質などには対応できない。
私は(A)と(B)の両方を組み合わせることで「環境にやさしい循環型社会」「持続可能な社会」を実現できると考えている。実際には、(A)では燃料電池車が例として挙げられる。確かに、燃料電池車の開発には今までかなりの時間を要し、触媒などに使われる白金や金は高コストである。しかしこの燃料電池車の価格が下がり、ガソリン車に代わって多くの人が選択する車となれば、酸素と水素だけで動き、排出される物質は水だけであるため、環境負荷を減らし、「持続可能な社会」に繋がる。
(B)では、生産工程でのデバイスの効率化が例として挙げられる。効率化には限界があるが、現在使用電力が大きく削減の余地があるボイラーやモーターに、高度な制御を取り入れることで「環境にやさしい循環型社会」に繋がる。またバイオプラスチック技術を導入することも有効である。プラスチックを燃やすときに廃止されるダイオキシンなどの有害物質を削減するため、自然に分解されるようなとうもろこしの原料の生分解性プラスチックなどに改善、改良を進めるべきだ。
上記のことから、私は2種類の製品開発の進め方をうまく組み合わせて取り入れることで、互いのデメリットを補い、環境への負荷を軽減できると考える。結果、「環境にやさしい循環型社会」「持続可能な社会」を実現できると思う。
持続可能な社会実現についての講評(抜粋)
2つの製品開発の進め方のメリットとデメリットについて、すばらしい見立てですね。自身の意見も、確かな知識をもとに、客観的に述べられています。上位で合格できると思われます。
論文の強みは、両アプローチを組み合わせることでデメリットの相互補完を図り、持続可能な社会実現への可能性を示唆している点です。例として挙げた燃料電池車や効率化の取り組みは具体的で理解しやすいものであり、提案が現実的であると言えます。
【さらに高みを目指して】
各アプローチの詳細な実現手法や具体的な障害についてはもう少し深掘りできると良いでしょう。また、提案の社会的・経済的影響や実現可能性に関する考察を加えることで、論文の信頼性と説得力が向上するでしょう。
↓
<修正文>
(A)の実現手法として、燃料電池車の開発においては、新しい触媒技術の研究や再生可能エネルギーの導入などが挙げられる。しかし、高コストな白金や金の使用や効率向上の課題があり、これらの障害を克服するためには国際的な協力や資金調達の強化が必要だ。
(B)において、生産工程のデバイス効率化の手法として、高度なセンサー技術の導入や制御システムの最適化が考えられれる。しかしこれには先進的な技術専門家の不足や既存の設備への改修コストなどが障害となる。これらの課題に対処するためには、教育・研究機関との連携や政府の支援策の拡充が必要だと考える。
↓
これにより、提案されたアプローチの詳細な手法と障害についての分析が深まり、実現可能性や課題の克服に向けた方針がより具体的になります。
【ガソリン車について】
もうガソリン車は廃止の流れということを踏まえておきましょう日本は完全に立ち遅れています。理由として、日本には大手のガソリン車メーカーが多いからだと考えられます。欧州、特にドイツにも多くのガソリン車メーカーがありますが、日本とは対照的にいち早くEV(Electric Vehicle電気自動車)への移行を宣言しています。
質問の回答(抜粋)
【質問1】・・・繋がる という表現が便利なので何度も使ってしまいます。他に、相応しい表現はありますか。
そのままの語彙の意味を踏襲するなら、「結びつく」となりますが、
少し言い回しを変えて、
(原文)環境負荷を減らし、「持続可能な社会」に繋がる。
(案1)環境負荷が減ることで、「持続可能な社会」の実現可能性が高まる。
(案2)環境負荷が減ることで、「持続可能な社会」の実現に近づく。
(原文)高度な制御を取り入れることで「環境にやさしい循環型社会」に繋がる。
(案1)高度な制御を取り入れることは、「環境にやさしい循環型社会」へ通じる。
(案2)高度な制御を取り入れることは、まさに「環境にやさしい循環型社会」への一歩だ。
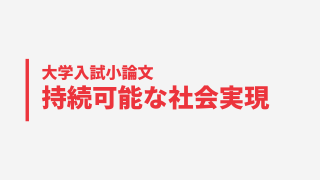
コメント