【高校古文】助動詞についてまとめています。
助動詞「めり・らむ・なり」
- 助動詞「めり」…目に見えるものの推定を表す助動詞。
- 助動詞「らむ」…目に見えないものを想像して推定する助動詞。
- 助動詞「なり」…聞こえてきたもので推定を表す助動詞。
助動詞「めり」の例
山陰の暗がりたる所を見れば、蛍は驚くまで照らすめり。(蜻蛉日記)
<訳>
山陰の暗くなっている所を見ると、蛍はびっくりするほど(あたりを明るく)照らしているようだ。
- 蜻蛉日記…平安時代に成立。作者は藤原道綱の母、名前は明らかになっていません。上中下の3巻からなり、主な登場人物は作者本人とその夫、藤原兼家です。夫婦と家族の物語を和歌で綴る、女流日記文学の最高峰。
助動詞「らむ」の例
さて、月ごろ経て、「今はよくなりぬらむ」とて見れば、 よくなりにけり。(宇治拾遺物語)
<訳>
そうして(ヒョウタンをつるしておき)、何ヶ月も経って、「今頃はちょうどよくなっているだろう」と思って(中を)見てみると、(ちょうど)よくなっていたのであった。
助動詞「なり」の例
我のみや 夜用は漕ぐと 思えれば 沖辺の方に 福の音すなり (万葉集)
<訳>
私だけ夜に舟を漕いでいるのだろうかと思われたが、沖の方でも指の音がするようだ
助動詞「る・らる」「す・さす・しむ」
- 助動詞「る・らる」…受け身・可能・自発・尊敬を表す助動詞(下二段活用)
- 助動詞「す・さす・しむ」…使役および尊敬を表す助動詞(下二段活用)
主語を確認
今は昔、治部卿道俊卿、後拾遺を選ばれける時、秦兼久、 行き向かひて、おのづから歌などや入る、と思ひてうかがひけるに、(宇治拾遺物語)
<訳>
今となっては昔のことであるが、治部卿の道俊卿が、『後拾遺和歌集』を撰集なさっていたとき、秦兼久が、 出向いていって、「ひょっとしたら(自分の)歌などが入るかもしれない」、と思ってうかがったが、
- 『宇治拾遺物語』(うじしゅういものがたり)…13世紀前半頃に成立した、中世日本の説話物語集である。『今昔物語集』と並んで説話文学の傑作とされる。「説話」とは、古くから民間で伝承されてきた民話や伝承のこと。笑い話や猥談なども収録されている点に特徴。
助動詞の「き」・「けり」
- 助動詞「き」…直接過去であり、自分の体験を表す助動詞。「き」の主語は、私(一人称)。
- 助動詞「けり」…間接過去(伝聞過去)であり、他人の体験を聞いて伝えるときに使う。「けり」の主語は他人になりまs。
「き」の主語も見抜く
粟津に来て、日次悪しとて三日居たるに、おぼつかなきこと限りなし。からうじて、よろしかりける日、京に入る。(古本説話集)
- 古本説話集(こほんせつわしゅう)…平安末期か、遅くとも鎌倉初期には成立したと見られる説話集。前半は世俗説話46話、後半は仏法説話24話を収録。有名な説話集『今昔物語集』、『宇治拾遺物語』、『世継物語』、また『醒酔笑』と共通する説話を多く有する。
<訳>
(男君は)粟津に来て、日取りが悪いということで三日じっとしていたが、気がかりなことこの上ない。やっとのことで、日取りが、まあまあ良かった日に、(男君は)京都に入る。
「けり」の主語も見抜く
俊恵に和歌の師弟の契り結び侍りし始めの詞にいはく、「歌はきはめたる故実の待るなり。われを真の師と頼まるれば、この事たがへらるな。」(無名抄)
- 無名抄…鴨長明による鎌倉時代の歌論書。先人の逸話や同時代の歌人に対する論評など多岐にわたる内容。
<訳>
(この私が)俊恵と師弟の契りを結びましたその始めの頃の言葉として(俊恵が)言うことには、「歌には究極の心得というものがあるのです。私を真の師匠と頼みにするのなら、この事にそむきなさるな。」

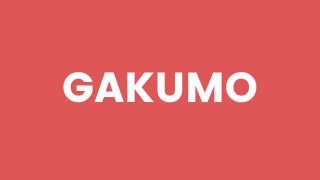
コメント