【高校古文】入試によく出る説話まとめです。
入試によく出る説話
「今は昔・昔・中頃・近頃」などで始まり、伝聞過去の「けり」で結ぶという形が多いのが説話の特徴です。章末にわかりやすいまとめ部分のあることが多いので、最初に章末の内容を確認してから読 み始めればスムーズに読解が進みます。
説話は、大きく仏教説話・世俗説話の2つのタイプに分類することができます。仏教説話は仏教に関するありがたい話や不思議な話、 人伝どがほとんどです。世俗説話は、様々な階級の人が登場し、たくましく生きる人間像を描写しています。
今昔物語集(未詳)
平安時代。千余りの説話から成り、天一 (インド)・震旦(中国)・本朝(日 本)の三部門に分かれている。説話の内容は、大きく仏教説話と世 俗説話に分類できる。芥川竜之介や菊池寛などが、この『今昔物語集』にある話をもとここから題材を にして執筆した作品を残しています。ほとんどの話が「今は音」で始まっているので、説話であることに気づきやすい。説話だと気づいたら、最初に章末を確認してから読解に入りましょう。
古本説話集(未詳)
平安時代。上巻には和歌に関する世俗説話、下巻には仏教説話を収めている。和歌に関する説話には、紀貫之・ 野小町・清少納言・和泉式部などが登場する。入試には、歌徳説話「和歌を上手に詠めば願いがかなう」「和歌は奇跡を起こす」などの話が出題されやすい。
発心集(鴨長明)
鎌倉時代。『方丈記』の鴨長明が著した仏教説話集。仏道に入って俗世への執着を絶ったり、極楽往生を願うといった話が多い。基本的にほとんどの話は、仏教的無常観を説くための例え話であると思って読むこと。各話には作者である鴨長明の感想が付け加えられている。
閑居友(鷹政上人?)
仏教説話集。作者自身の感想が色濃く表れている点が特異である。平家滅亡後の関係者の話(特に女性の説話)が頻出する。
今物語(藤原信実)
短い説話(小話)五三編から成る。和歌を中心とした「みやび」の世界を織りなす逸話や、貴族社会の裏話や失敗談などの世俗説話が収録されている。
宇治拾遺物語(未詳)
鎌倉時代。仏教説話が8話、世俗説話が四話ほどあり、場所も『今昔物語 集』と同じく三国(日本・中国・インド)にまたがっている。全体として教訓性・啓蒙性が弱く、破戒僧、盗賊、「こぶ取り爺 さん」の話など、笑いやおかしみにまつわる庶民的な説話を多く収録している。
十訓抄(未詳)
鎌倉時代。約280話の世俗説話を十編に分類して掲載している。インド・中国・日本の説話の中から教訓的なものを集めてある。説話の読解法に従って読解を進めていくこと。
古今著聞集(橘成季)
鎌倉時代。約700話の世俗説話が年代順に 収められてある。平安貴族社会 に対する強い憧憬の念が見られる。『今昔物語集』、『宇治拾遺物語』、そしてこの『古今著聞集』 が三大説話とされる。
沙石集(無住)
室町時代。仏教の教理をわかりやすく説く仏教説話など、約の話を収め、十巻からなる。説話の読解法に従うこと。
御伽草子(未詳)
室町時代。教養の高くない人々のための絵入りのわかりやすい短編物語。童話・空想話・教訓話などがその主な内容。
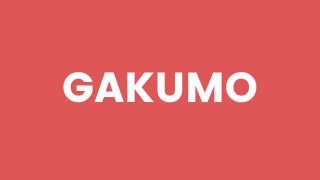
コメント