【日本史探究対策問題】戦国・安土桃山時代の問題です。
【対策問題】戦国・安土桃山時代の問題
【問1】戦国時代から全国統一へと向かう過程で南蛮貿易と宣教師の布教活動があたえた影響を、次の語句を用いて120字以内で説明しなさい。
( 鉄砲・天正遣欧使節・バテレン追放令 )
【問2】次の問いに答えなさい。
(1)桃山文化を象徴する天守閣や櫓・郭などをもつ建築物は何か。
(2)池田輝政の居城として慶長年間に竣工した平山城で、五層七重の大天守に3個の小天守をつなぐ連立式天守閣をもつ城郭を何というか。
(3)豊臣秀吉が晩年に築城して居城とし、江戸時代に廃城とされ、解体された京都の城郭を何というか。
(4)桃山文化を代表する絵画には城郭内の裸や屏風に描かれたものがあるが、このような絵画を何というか。
(5)障壁画の絵画に用いられた手法で、金箔地に群青や緑青などを厚く塗ったものがある。これを何というか。
(6)安土城・大坂城などの障壁画を描き、桃山時代に狩野派の発展の基盤を築いた人物で、「唐獅子図屏風」の作者でもある人物は誰か。
(7)濃彩の装飾的な作品とともに、水墨画にも優れた作品を残した桃山時代の代表的画家を2人あげよ。
【問3】次の2つの分国法の条文から、戦国大名が農村と農民をどのような方法で支配しようとしていたか、80字以内で説明しなさい。
- 朝倉孝景条々(朝倉敏景十七箇条)…「朝倉が館之外、国内□城郭を構へさせまじく候。惣別分限あらん者、一乗谷へ引越、郷村には代官ばかり置かる可き事。」
- 塵芥集…「百姓、地頭の年貢所当相つとめす、他領へ罷り去る事、盗人の罪科ハたるへし。」
【解答】戦国・安土桃山時代の問題
【問1】鉄砲の伝来は、それまでの戦法や城の構造に変化をもたらした。貿易をのぞむ大名は、布教活動を保護した。宣教師のすすめで天正遣欧使節を派遣したキリシタン大名のなかには、教会に領地を寄進する者もいたため、バテレン追放令で宣教師は国外に追放された。
【問2】
(1)城郭
(2)姫路城
(3)伏見城
(4)障壁画
(5)濃絵
(6)狩野永徳
(7)長谷川等伯、海北友松
【問3】家臣を城下町に移住させ、農村への直接的な影響力を失わせようとした。また、農民の村内定住を強制し、年貢を確実に納入させることで、支配力を農村までおよぼそうとした。

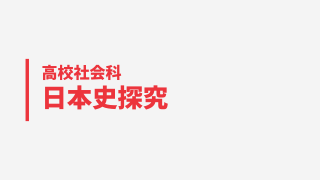
コメント