【大学入試小論文】ジェンダー平等・女性差別問題のポイントについてまとめています。
女性問題のポイント
女性問題は女子大・短大では頻出中の頻出。だが、それ以外でも、法学部などで近年、女性の人権、セクハラ問題といった形で出題される。
女性差別の実態
男女雇用機会均等法の1986年から実施されて多少の改善はされてましたが、まだ男女の就職の機会は平等ではない。女性はさまざまな点で差別されている。
女性が差別されるのは、女性は家にいて、家事や育児を行うべき存在とみなされ、社会に進出すべきだとは思われていなかったためだ。 しかも、女性は子どもを産むために、企業にとって男性に比べて効率がよくない。結婚して、子どもをつくって仕事をやめる。子どもの病気、学校の行事といったことで、仕事が男性並みにできない。
そんなわけで、企業は女性を雇おうとない。雇っても重要な地位につけない。
男女平等を目指して
いまだに性別役割分担の考えが残る。「男性は仕事、女性は家事と育児」である固定概念のもと 採用や昇進などで女性が不利。セクシュアル・ハラスメントも問題である。
男女が対等に参画し活動できる社会をめざし、育児休業の取得促進、保育所の整備などが求められる。
<関連法案>
男女平等参画社会基本法(令和2年法律第2号):男女が共に社会に参画し、その力を最大限に発揮するための基本方針を規定しています。労働市場における男女の平等な機会や待遇を確保することが含まれています。
男女雇用機会均等法(昭和44年法律第76号):雇用において男女の平等な機会を確保し、男女の雇用機会均等を促進することを目的とした法律です。企業には、雇用機会均等の確保や採用から退職までの一連のプロセスにおいて男女差別の防止が求められます。
男女共同参画社会基本法(平成20年法律第113号):男女が共に社会において活躍するための基本的な方針を定めています。職場や家庭などでの男女平等な関与を促進し、社会全体における男女の平等な地位を目指します。
介護休業法(平成11年法律第76号):介護を必要とする家族がいる労働者が、その介護のために仕事を一時的に休業できるようにするための法律です。男女平等の観点から、男性も介護休業を取得することが奨励されています。
育児介護休業法(平成7年法律第76号):労働者が子供を出産し、または養子縁組をする際に、育児のために仕事を休むことができるようにする法律です。男女双方が育児休業を取得できるようになっており、男女平等を促進しています。
男女の役割分担
すべての女性が家で子どもを育てるのに向いているわけではない。「男は社会に出て仕事をし、女性は家で家事をする」という役割分担も人為的なものでしかない。
女性は、しとやかであるように教育されてきたにすぎない。もちろん、女性は子どもを産むことが できるし、筋力などが肉体的に男性に比べて弱いのは、否定できない。
男と女は、肉体的にも、精神的にも異なる。だが、そうした違いを認めて、女性らしさを強 制せず、みんなが自分らしく生きる必要がある。そのためには、強制的な男女の役割分担をなくす必要がある。
男女平等の社会
「男は外で働いて…」という分担をやめて、男女が協力して働き、協力して家事をし、協力して育児をしようとする。
そのためには、スウェーデンなどのように、男性にも育児休暇を認めるという制度を設ける必要 があるだろう。
そうすることによって、男性も「社会で働いて、妻子を養わなければ男として恥ずかしい」という重圧から解放されることになる。
男と女が自分に適したことをして、それぞれ正当に評価される社会、それこそが男女平等の社会と言えるだろう。
知っておきたいジェンダー問題のキーワード
■男女の役割分担
「男はこうあるべきだ」「女はこうあるべきだ」という役割を強制したら、一人一人の個性を認めないことになる。性によって決めつけるのでなく、個性を重視すべきだ。
■家制度
女性は家制度の犠牲者だと言われる。結婚は他家に入ることであり、自分の生まれた 家から出されることを意味する。家を重視するのでなく、個人を視することが女性差別から 女性を解放することにつながる。
■セクシャル・ハラスメント
男性が女性を仕事 のパートナーではなく、セックスの興味の対象として考えて、仕事上の地位を利用して女性との関係を迫る。女性を同僚としてみない男性のあり方に問題があると考えられる。
■夫婦別姓
現在は、ほとんどの妻が夫の名前を名乗っている。だが、それは家制度の名残なので、妻も自分らしさを守って、夫と別の姓を名乗っていいのではないかという意見がある。これには、「家族は一つであるべきだ」という反論があり、議論されている。
■ジェンダー平等
男女や他の性別において、法的・社会的・経済的な権利や機会が平等である状態を指します。ジェンダー平等は、男女が同じ権利と責任を共有し、差別がない社会を追求する理念です。
■ジェンダー・アイデンティティ
個々の人が自らを男性、女性、あるいはその他の性別として認識する内面的な感覚を指します。ジェンダー・アイデンティティは、生物学的な性別とは異なり、社会的・文化的な要素も含まれます。
■セクシズム
特定の性別に対する差別や偏見を指す用語で、主に女性に対する差別を指すことが一般的です。セクシズムは言動や構造的な不平等を含む広範な形態をとります。
■トランスジェンダー
トランスジェンダーは、生物学的な性別と自らのジェンダー・アイデンティティが一致しない人々を指します。例えば、生物学的には男性であるが、女性として自己認識する場合などがあります。
■パトリアーキー
社会が男性中心主義で組織され、男性が特権を持ち、権力を支配する構造を指します。パトリアーキーは、様々な形で社会構造や慣習に浸透しており、ジェンダー不平等を維持する要因とされています。
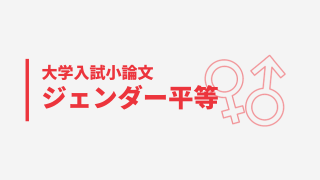
コメント