【大学入試小論文】東京農業大学農学部農学科(2020年度・推薦入試)小論文の解答例です。改題となります。
【実際の問題】近年注目されているスマート農業は、「ロボット技術やICTなどの先端技術を活用し、超省力化や高品質生産などを可能にする新たな農業」とされる。今後のスマート農業の導入のメリットと課題についてあなたの考えを述べよ。
【改題】日本の農業が抱える問題がスマート農業によりどのように解決されるのか、またスマート農業に携わる農家の人にはどのような能力が求められるのか。あなたの考えを 800 字程度で述べなさい。
【改題】東京農業大学農学部(2020年度)小論文の解答例
日本の農業は、農家の高齢化とともに、後継者が不足しているという課題を抱えている。生命を支える農業が衰退するということは食料自給率の低下にもつながりかねない。
これらの状況に至った原因は2つある。まず、農業という職業は肉体的な負担が大きいことだ。現代はサービス業など第3次産業就労者人口が多い。次に、生計を立てる難しさだ。最近は有機農業に興味を持ち、農業を始める若手が多いが、上手くいかずに辞めてしまうという新聞を読んだことがある。
これらの課題解決は、スマート農業の自動化によってもたらされると考える。具体例として、自動トラクターが挙げられる。以前、私が農家を訪ねた際、真夏の長時間作業の苦悩を耳にした。自動化することで、このような肉体的負担を減らせるだけでなく、農法技術を持っていなくとも農業を始めることができる。
確かに、スマート農業だと操作的技術が必要ではないかという意見も想像できる。しかし、慣行農業は天気や土壌の様子、害虫被害などに臨機応変に対応する技術が必要とされる。対して、スマート農業は、操作方法を身につけさえすれば、AIなどを用いた水や天気、育成状況の管理システムにより、効率的な分析が可能だ。その結果、臨機応変に、失敗と負担の少ない農業を可能にする。
スマート農業に携わる農家の人に求められる能力は、新しい技術を受け入れてみようという積極的な行動力だ。初めは操作方法の習得の苦労や初期導入の費用の負担があるが、生産性の向上は長期的に農業を続けるためには不可欠である。農家の意識改革だけではなく、政府や大学によるスマート農業の普及への支援を行うことで、日本はスマート農業を積極的に取り入れ、農業を活性化していくべきだ。
【改題】東京農業大学農学部(2020年度)小論文の講評(抜粋)
論文は日本の農業課題とスマート農業の潜在的解決策を明確に示しています。高齢化と後継者不足の問題をスマート農業の自動化が軽減するという提案は有望であり、特に自動トラクターの例が具体的で説得力があります。
一方で、もう少し反対意見や批判的な見方への対応があるとよりバランスが取れた論文になるでしょう。スマート農業への技術的な懸念や初期投資の問題に触れ、それに対する対策や調整の可能性を考慮することで、論文の厚みが増すでしょう。
能力に関する議論は具体的で理解しやすい一方、農家の積極的な行動力だけでなく、スマート農業を支援する制度や教育の必要性にも触れるとより洗練されます。締めくくりも強力で、スマート農業の導入が新しい息吹をもたらす可能性に期待を寄せている点が印象的です。

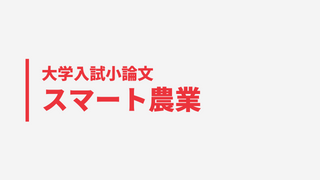
コメント