【高校政経】覚えておきたい法律一覧(共通テスト対応・よく出る編)です。
覚えておきたい法律一覧
労働関係の法律、環境問題の法律、社会保障の法律、消費者問題の法律、農業の法律、企業の法律、国際関係の法律、選挙の法律、地方政治の法律についてまとめています。
労働組合法
1945年制定、1949年全面改正。労働組合を自主的につくる、団体交渉を行う、労働協約を結ぶ、争議行為を行うことなどを認める。
労働関係調整法
1946年制定。労働関係の調整を図り、労働争議を予防・解決して産業の平和を維持することを目的とする。労働委員会が斡旋・調停・仲裁・緊急調整などを行うことを規定している。
男女雇用機会均等法
1985年に女子差別撤廃条約に批准。これを受けて男女雇用機会均等法(1986年)が制定された。1997年、2006年に改正。女性差別やセクシャアル・ハラスメント(セクハラ)防止が企業に義務づけられた。
パートタイム労働法
1993年制定。パートタイマーと正規雇用労働者の格差是正が目的。パートには女性が多いため、男女格差の是正につながると期待。
育児・介護休業法
1991年に成立、1995年に改正。育児・介護を目的とした休業を労働者の権利と認めた。時間外労働の免除なども規定。男性の育児・介護休業も認められているが、現状、休業をするのは大部分が女性である。
公害対策基本法
四大公害の発生を受け、1967年に公害防止と生活環境の保全を目的として制定された。1993年の環境基本法施行に伴い廃止された。
環境関連14法(公害関係14法)
1970年の「公害国会」で大気汚染防止法・水質汚濁防止法など関連法を整備。総量規制が採用された。1971年に環境庁(現環境省)を設置。
環境基本法
1993年成立。大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭の7種類を公害と規定。国・地方公共団体・事業者・国民の責務が明記された。
循環型社会形成推進基本法
2000年制定。循環型社会の形成を推進するための枠組みとなる法律。廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立された。
介護保険法
1997年制定。介護が必要と認められた人に介護サービスの費用が給付されるようになった。利用者の負担は原則として1割。
エリザベス救貧法
1601年、イギリスで成立。「土地囲い込み」によって増加した浮浪農民を救済した。国家による公的扶助の原型と評価された。
社会保障法
1935年、ニューディール政策の一環としてアメリカで成立。失業保険・老齢遺族年金保険などを内容とした。
消費者保護基本法
1968年制定。消費者の生活と権利を守る。2004年に全面改正され、消費者の自立支援をめざす消費者基本法となった。
製造物責任法(PL法)
1994年制定。製品に欠陥があることを立証すれば、製造者に賠償責任があるという無過失責任制度が定められた。
消費者安全法
地方公共団体が商品の欠陥を把握した場合に、直ちに消費者庁への報告を義務付けている。
農業基本法
農業と他産業との所得格差の縮小を目的として制定。畜産・果樹・野業など、需要の増加が見込まれる農作物の選択的拡大を図り、経営規模の拡大と機械化による自立経営農家の育成を目指した。
食糧法
1995年、食管法に代わって制定。米の大幅な規制緩和。
食料・農業・農村基本法
1999年、農業基本法に代わって制定。食料の安定供給の確保、環境や文化・農業の多面的機能, 農村振興を重視。
中小企業基本法
1963年に制定。大企業との格差是正・保護育成を目的とした。1999年の改正で、中小企業を日本経済のダイナミズム(活力)を生み出す源泉ととらえ、多様な発展を支援していく方針になった。
中小企業金融円滑化法
2009年に制定。銀行による「貸し渋り・貸しはがし」 に対する対策がとられた。
大規模小売店舗法(大店法)
各地域の中小小売業の保護を目的とし、大型店の市街地中心の出店等を規制していた法律。アメリカから強く規制緩和を求められ、廃止された(2000年)。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)
大店法に代わって制定され、大規模 店舗出店に向けた生活環境整備が進められた。各地域に巨大ショッピングモールがつくられ、地方の市街地・商店街は次々にシャッター街化した。
国際慣習法
長い間の外交の過程で認められてきた国家間の暗黙の合意。領土の不可侵、内政不干渉、公海自由の原則、外交特権など。
公職選挙法
1950年に制定。選挙権、被選挙権、選挙区, 投票方法、選挙運動。選挙管理などを定めた公職の選挙に関する総合的な基本法。
地方分権一括法
1999年に成立し、これまで国の指揮・監督下で処理されてきた機関委任事務が廃止された。
NPO法
1998年。行政や企業と連携して事業を行うNPOを支援。ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的。
構造改革特区法
2002年。教育、物流、農業、社会福祉、研究開発等の分野における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図る。
地方分権改革推進法
地方分権改革をさらに進める。2007年4月1日施行。施行後3年で効力を失う限時法であり、平成22年4月1日に失効した。
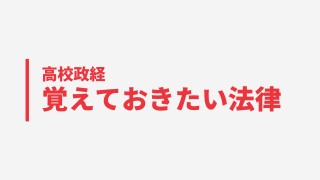
コメント