【高校地理総合】気圧帯の種類と特徴についてまとめています。
気圧帯の種類と特徴
大気の大循環によって、地球にはいくつかの低圧帯と高圧帯が形成されている。それぞれの気圧帯における空気の動きを覚えておく必要がります。
低緯度低圧帯
赤道低圧帯、熱帯収束帯、赤道無風帯ともいう。太陽エネルギーを効率よく受け取ることで地表付近の空気が膨張し(密度が低下)、強い上昇気流を生じる。積乱雲が発達することで、毎日午後に激しい降水(スコール)が生じる。
<気圧の性質>
- 気圧が低くなると、空気が膨張して、温度が下がる。
- 空気が膨張するとき、フラスコ内の空気が露点以下になち、水蒸気が水滴になって白くくもる。
- 気圧が高くなると、空気がおし縮められて温度が上がって、水蒸気にもどり見えなくなる。
中緯度高圧帯
亜熱帯高気圧ともいう。赤道方面で上昇した空気が、緯度20~30度付近で下降気流となる。雲の発生が抑えられることで、降水量は少ない。この緯度帯には乾燥地域が広がる。
高緯度低圧帯
寒帯前線ともいう。低緯度方向から吹き込む暖気(偏西風)と、高緯度方向から吹き込む寒気(極風)が接する境界面に前線が形成される。激しい降水はみられないものの、降水のやや多い、湿潤な気候をもたらす。
- ヨーロッパ北西部…沿岸を流れる暖流の北大西洋海流と偏西風の影響で高緯度のわりには温暖な西岸海洋性気候。
極高気圧
寒冷な極地域では空気が収縮し、高気圧となる。下降気流が生じ、周囲に向かって寒気が吹き出している。雲は発生しにくい。
雲のでき方
大気中に、直径0.01~0.07mmくらいの水滴や氷晶がうかんだものを雲といい、雲は上昇気流のあるところにできます。雲をつくる水滴や氷晶が、大気中にうかぶのは、これらの雲粒が非常に小さいために、落下速度が小さい上に、雲は上昇気流の中にできるためです。
以上が、【高校地理】気圧帯の種類と特徴となります。
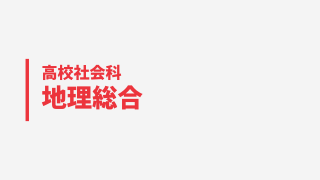
コメント