【大学入試小論文】北海道大学教育学部小論文(2017年度)解答例です。
【改題】課題文を読んで、筆者の主張に対する自分の見解を述べ、学校が「人が育つ集団」であるためについて述べよ。
学校が「人が育つ集団」であるために論文
私は、著者の主張に賛成だ。筆者が述べるように、集団は、不均一であることに意味があり、均一ではないお互いの役割を尊重し信頼することが求められていると思うからだ。
学校の先生が皆、優しければ、将来生徒が先輩や上司に叱られたとき、それを跳ね返す強さは育たなくなり、学校の先生が皆、厳しければ、生徒は先生に相談できなくなる可能性が大きいだろう。私の経験からも、当初、厳しくて恐いベテランの看護師さんがいなくなることで病棟がもっと平和になり、のびのびしたいい雰囲気になると思っていた。しかし、実際は、その看護師さんがいることによって、一人ひとりの役割にバランスがとれていた。このことからも、集団は、不均一であることに意味があり、均一ではないお互いの役割を尊重し信頼することが求められている。不均一である役割は、対立的なものではなく、両者がいることによって成り立つと考える。
以上のことを踏まえ、私は、学校が「人が育つ集団」であるためには、一人ひとりが多様な価値観を受け入れ、自分とは異質であると思えるような人とも共生していかなければならないと考えている。それは、同じような人が集まると、役割のバランスがとりにくくなったり、集団間での衝突などが少なくなり、不毛かつ人を育むことができなくなると思うからだ。
しかし、現代社会は、少数派の人や異質な人を排除しようとする動きが強いと思う。これは、少数派の人や異質な人が社会の中で孤立してしまうだけでなく、多数派の人も偏った価値観にしかふれられなくなったり、多様性を受け入れられなくなったりという面でも、問題だ。学校教育の現場では「少数派」や、「異質」といった目をなくし、皆平等という考えをもつことが課題になるだろう。つまり、差別意識をなくしていくということだ。差別意識をなくすことができれば、「排除」という考えもなくなっていくと考える。
学校が「人が育つ集団」であるために講評(一部抜粋)
【甘め】
論点がはっきりしており、論理的な展開が見られます。主張を裏付けるために具体的な例も挙げられており、説得する力があります。また、論文の構成は、適切な構造でまとめられており。導入、本論、結論が明確であり、段落ごとの移行も滑らかです。
【厳しめ】
一般論に終始するのはいいのですが、根拠や理由に説得力が欠ける。うわべだけの論文といえます。尊重する、多様性を認める、差別をなくすとか、どこでもあるような意見で、それはそれでいいのですが、なぜ大事なのか?皆、それらは大事だと思っています。にもかかわらず、なぜそんな社会が実現できないだろう?そういう点を織り込むこと考察もあるとよかったと思います。
【確認事項】
【1】「現代の時代は、少数派の人や異質な人を排除しようとする動きが強いと思う。」とありますが、たとえば?
不均一であること、多様性が大事なのは、昔に比べると緩和されつつあるのでは?インターネットの普及により、小さな声も拾えるようになったのでは?マイノリティの人たちの声が聞こえてきませんか?政策を見ても、同性愛の結婚、バリアフリーの拡充、外国人に配慮した標識・アナウンス、里親制度の普及、女性の社会進出などなど数知れません。
【2】差別意識は、どうすればなくなるの? 具体性がほしいところ。差別をなくせばいいなどというのは、当たり前でしょう。なぜ差別がなくならないのか?という点において、意見が聞きたいのです。
学校が「人が育つ集団」であるために一般論
- 多様性を尊重: 異なる文化、バックグラウンド、および価値観を受け入れ、尊重することで、生徒たちが豊かな視野を持ち、相互理解が深まります。
- コミュニケーション強化: 適切なコミュニケーションスキルを養い、感情や考えをオープンに共有する環境を構築。これにより、協力や共感が促進されます。
- 個々の強みを引き出す: 生徒たちが持つ異なる才能や興味を発見し、それを伸ばすサポートを提供。個々の個性が尊重され、育まれる環境が必要です。
- 共感と協力の教育: 共感力や協力力を育む教育プログラムを導入。仲間意識や他者への思いやりを醸成することが重要です。
- 成長志向の文化: 失敗を恐れず、それを学びととらえる文化を醸成。ポジティブなフィードバックや挑戦への支援が、生徒たちの成長意欲を刺激します。
学校が「人が育つ集団」であるために視点
①「人が育つ集団」は、全員参加型であることがその前提にあると考える。
たとえば、学校の授業を考えてみる。授業は、先生がするものだと思われがちだが、生徒も一緒になって授業を作るという視点があれば、おのずとその集団である学級は成長していくだろう。それは、生徒が自発的に参加しているからだ。
②「人が育つ集団」は、当事者意識をそれぞれが持つという集団であると言える。
ここで述べる当事者意識は、「どんな時・状況も、自分にできることは必ずある」という意識だ。この意識があれば、自分とは価値観が違う人がいる集団においても、その人や集団に対して、自発的な行動が起こせるだろう。それぞれが当事者意識を持つということは、支え合うことになる。それが認め合うということにもつながっていくと考える。
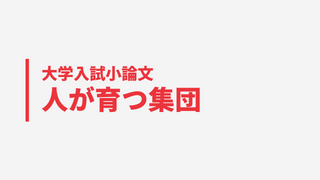
コメント